
オイシサノトビラ
音楽家|haruka nakamura
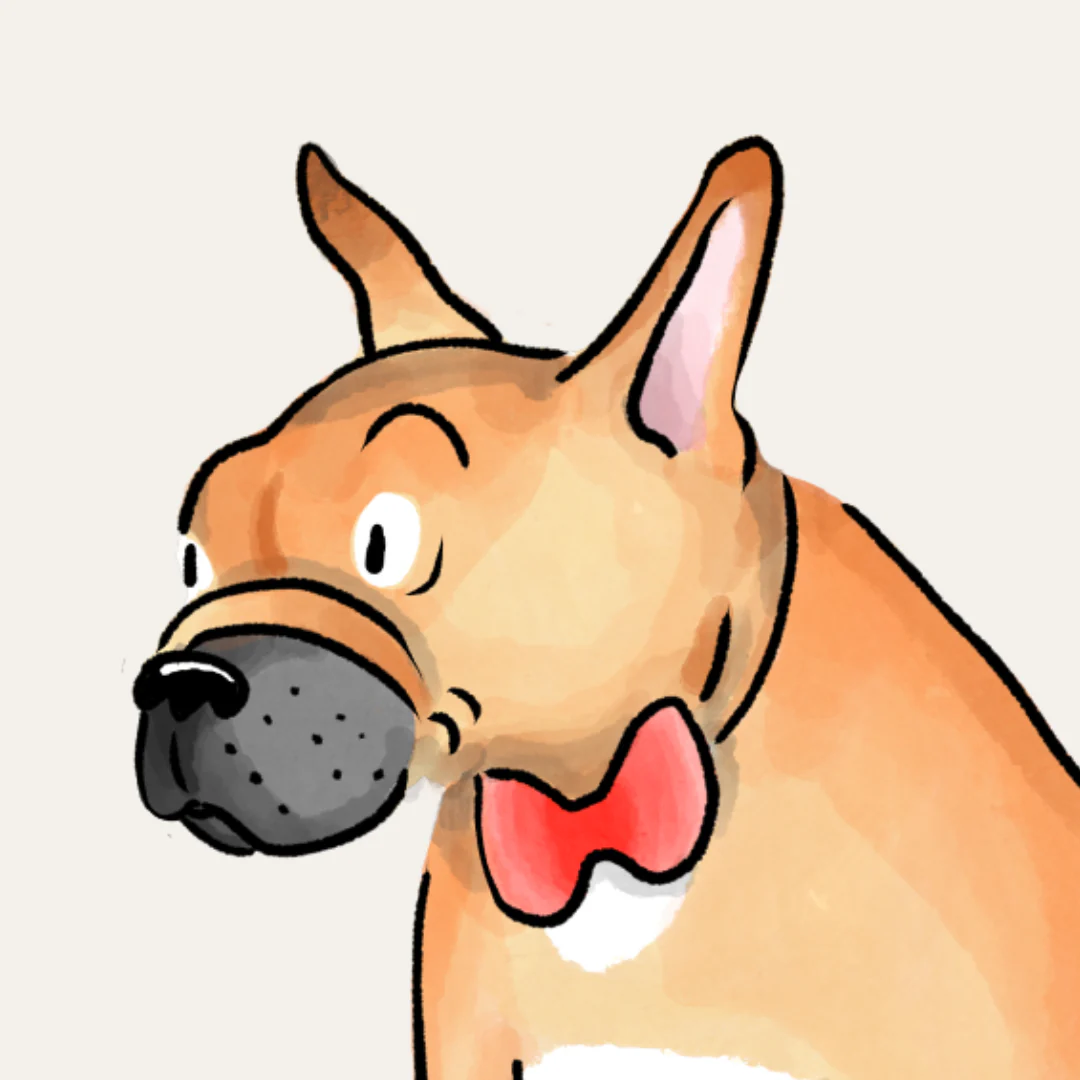
オイシサノトビラ
──── 青森で生まれ育ち、15歳にして音楽で身を立てるために上京したharuka nakamuraさん。
「音楽のある風景」をテーマに、いくつかのオリジナルアルバムのほか、数多くのドラマや映画、CMなどの音楽を担当。最近では映画『ルックバック』の音楽を手掛けたことでも脚光を浴びている。
そんなharuka nakamuraさんは食のお仕事にも携わることが多い。『POPEYE Web』で「A COOKING GUIDE FOR CITY BOYS 原川慎一郎の 定番料理のニューディール」という連載コンテンツの音楽を担当したり、さまざまな料理人たちと全国各地で料理と音楽のコラボレーションを実現したりと、斬新な取り組みを次々と展開している。
こうした音楽活動と食へのこだわりの根幹にはどのような記憶や思いがあるのか。これまでの歩みとあわせて語ってもらった。
オイシサノトビラ
生まれ故郷である青森の風景が、haruka nakamuraさんの音楽の原点になっているという話を耳にしたことがあるのですが、まずはそのあたりのエピソードからお話しいただけますか。
haruka nakamura
母がピアノ講師だったので、物心がついた頃からピアノをよく弾いていたんです。それ自体はよくあることだと思うんですが、ある日、ふと夕暮れの風景のなかに「音楽」があることに気がついたんですよね。その時に感じ取った音楽に感動し、急いで自宅のピアノでメロディにしてみたんです。それが僕にとって「音楽のある風景」を感じ取った最初の瞬間だったように思います。
以来、僕は「音楽のある風景」を探し求めてきました。と同時に、いつの頃からか、音楽が常に自分のなかで鳴っていることに気がついたんです。心に残る風景に出会った瞬間、音楽が僕の内側から大きく鳴り響いてくるんです。この感覚は今も大切にし続けていて、僕の音楽活動の大切なテーマになっています。
オイシサノトビラ
素晴らしい風景と出合った瞬間の感覚を大切にしているのだと感じました。
haruka nakamura
実は小学生の頃にピアノを一度やめてしまったこともあり、譜面を読んだり、書いたりすることは今でも決して得意ではないんです。なので、楽曲を譜面に残すことはほとんどなくて、感覚のなかに残している場合がほとんどで、ピアノを弾く時も譜面台には何も置かないか、曲順を書いたメモだけを置くようにしています。あとは、鈴とか鐘とか、鳥の声が鳴るオモチャとか、譜面とはまったく関係のないものを置くこともありますね。
いずれにしても、僕が音楽に向き合う時に頼りにしているのは感覚だけで、演奏も作曲のスタイルも基本的には即興です。まったく同じように弾けないからこそ、毎回、新鮮な心持ちでファーストテイクに臨むことができていますし、そのファーストタッチの一瞬の煌めきが大好きなんです。
オイシサノトビラ
そのほかにも、記憶に残っている風景があれば教えてください。
haruka nakamura
青森で眺めた夕暮れとは別に、もうひとつ記憶に残っている夕暮れがあります。それはNujabesさんというアーティストと一緒に見た鎌倉の夕暮れです。僕にとってあこがれの存在だったNujabesさんとともに音楽制作に携われた夢のような記憶が、その景色とともに僕のなかに鮮明に残り続けているんです。Nujabesさんが交通事故に遭い、天国に行ってしまってから10年以上が経ちましたが、僕は今でもよく鎌倉の海に夕暮れを見に行きます。江の島ごしにゆっくりと沈んでいく夕陽と波音はいつも僕もやさしく包んでくれるんです。
オイシサノトビラ
一度は音楽活動をやめようと思ったことがあるそうですね。
haruka nakamura
Nujabesさんが亡くなった後、僕は音楽活動をやめようかと思いつつ旅に出たのですが、その時に読んだ星野道夫さんの『旅をする木』(文芸春秋)が音楽を続ける道に進むことを後押ししてくれました。振り返ってみると、僕は星野道夫さんの言葉や写真にずっと支えられてきました。それだけに先日、星野さんの写真展で彼の写真や言葉とコラボした演奏会を催すことができたのは感無量でした。2024年の帯広美術館での星野道夫巡回展「悠久の時を旅する」に際しては、奥様だった星野直子さんの朗読とコラボした演奏会を開くことができ、最高の記憶になりました。
オイシサノトビラ
人との出会いからも多くのインスピレーションが得られているのですね。
haruka nakamura
そういう意味では、Nujabesさんには今も影響を受け続けています。残されているスタジオに足を運ぶたびにいろんな学びや気づきが得られるんです。本棚に村上春樹さんの本があるのを見て読むようになったのもそうですし、星野道夫さんの写真を彼がアルバムジャケットにしようとしていたことを知って何だか感慨深くなったり……。もうNujabesさんと言葉を交わすことはできませんが、スタジオに行くと、彼の本棚やレコード棚、そして残してくれた数々の音楽などと心の会話ができるような感覚があるんです。年を重ねるにつれて、その感覚はどんどん研ぎ澄まされていっているような気がします。

オイシサノトビラ
『POPEYE Web』では「A COOKING GUIDE FOR CITY BOYS 原川慎一郎の 定番料理のニューディール」という連載コンテンツの音楽を担当されていますね。そのほかにも、いろんな料理人の皆さんとコラボしているようですが、そこにはどのような思いがあるのでしょうか。
haruka nakamura
僕はどういうわけか、他ジャンルの方とコラボすることが多く、特に料理人とのコラボが多いんですよね。なかでも「BEARD」(長崎県雲仙市)の原川慎一郎さんとはとても親しくて、星野道夫さんの感性にも共感してくれました。また、原川さん自身が心地よい低音の持ち主なので、音楽面でもコラボしています。たとえば、原川さんが星野さんからインスピレーションを受けた自作の詩を朗読する『LONG JOURNEY』などはその一例です。音楽と料理がここまで垣根を越えてコラボするケースはあまりないと思います。

photo : haruki anami
また、料理家の細川亜衣さんが自らディレクターとなり、料理教室や料理会などを開催している「taishoji」(熊本県熊本市)で、長年にわたって料理と音楽の会「食卓とピアノと」を続けています。亜衣さんの特別なホームグラウンドだからこそできる、その日だけの料理と音楽のセッションを季節ごとに4回行いました。今年からは亜衣さんが命名した「MUSICUCINA」(MUSICA〈音楽〉×CUCINA〈料理〉を掛け合わせた造語)という新たなタイトルで、ピアノやギター、さらには花や庭なども取り入れた空間演出を目指しています。
ちなみに、亜衣さんは2024年から毎月、『料理』という映像作品をYouTubeなどで発表しています。亜衣さんの美しい料理の映像に僕の音楽を添えたもので、年間12本を制作する予定になっており、現在は7本分が公開中です。ゆっくりと深呼吸をするようなひと時を味わっていただけるかと思います。
おかげさまで、さまざまな料理人の皆さんとコラボさせていただいていますが、音楽と料理のコラボとひと口に言っても、それぞれがまったく違う個性やコンセプトで彩られています。他ジャンルのプロフェッショナルとこのような形でコラボさせていただけるのは本当に刺激的ですし、ありがたいですね。

photo : haruki anami

photo : haruki anami

photo : haruki anami

photo : haruki anami

photo : haruki anami

photo : haruki anami
後編につづく。
profile

haruka nakamura ハルカ・ナカムラ
青森出身 / 音楽家
15歳で音楽をするため上京。2008年1stアルバム「grace」を発表。2024年劇場アニメ「ルックバック」劇伴音楽と主題歌を担当。蔦屋書店の音楽「青い森」シリーズ4作品を発表。ジャケット写真は全て写真家・川内倫子が担当した。アパレルブランドTHE NORTH FACEと四季に渡るコラボレーションアルバム4作品を発表。敬愛する写真家・星野道夫の写真展にて演奏会「旅をする音楽」を東京都写真美術館、帯広などで開催。国立近代美術館「ガウディとサグラダファミリア展」NHKスペシャルのテーマ音楽などを担当。代官山 蔦屋書店にて展覧会「本屋の片隅、音楽家の展覧会」を行う。展覧会の記念に旅の風景を自身が撮りためた写真集「音楽のある風景」を発表。Nujabesと音楽制作を共にした時間があり、hydeoutから「MELODICA」「Nujabes PRAY Reflections」などを発表している。初期作品からほぼ全てのアルバムがアナログレコード化され再発売を続けている。NHK「ひきこもり先生」Hulu「息をひそめて」任天堂「どうぶつの森」などドラマ、映画、CMの音楽を多く手掛ける。長い間、旅をしながら音楽を続けていたが、2021年より故郷・北国に暮らし音楽をしている。
https://www.harukanakamura.com/
連載
オイシサノトビラの扉
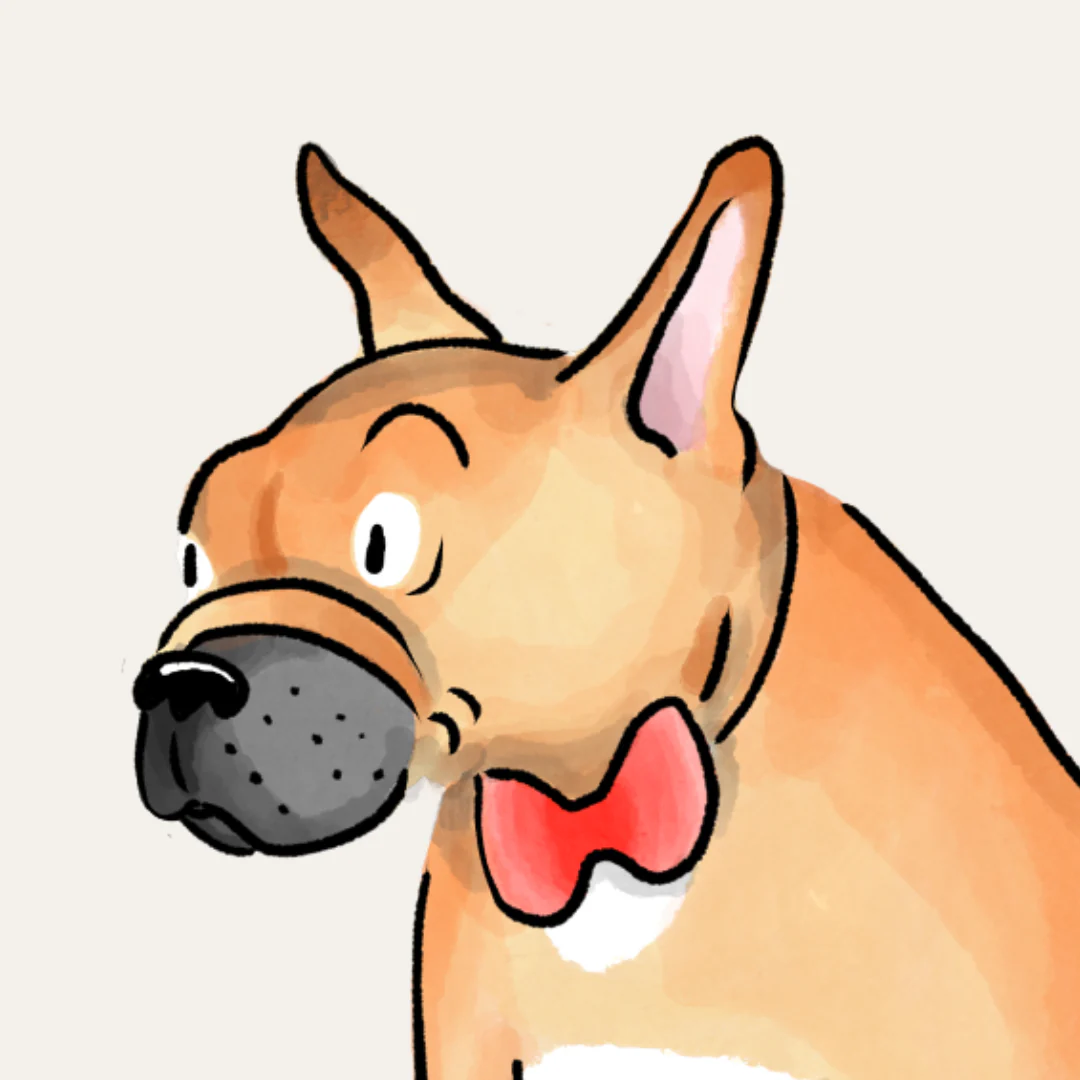
オイシサノトビラ
「おいしさって、なんだろう?」をテーマに、その人の生きる素となるような食事との出合いやきっかけをつくることを目指しています。