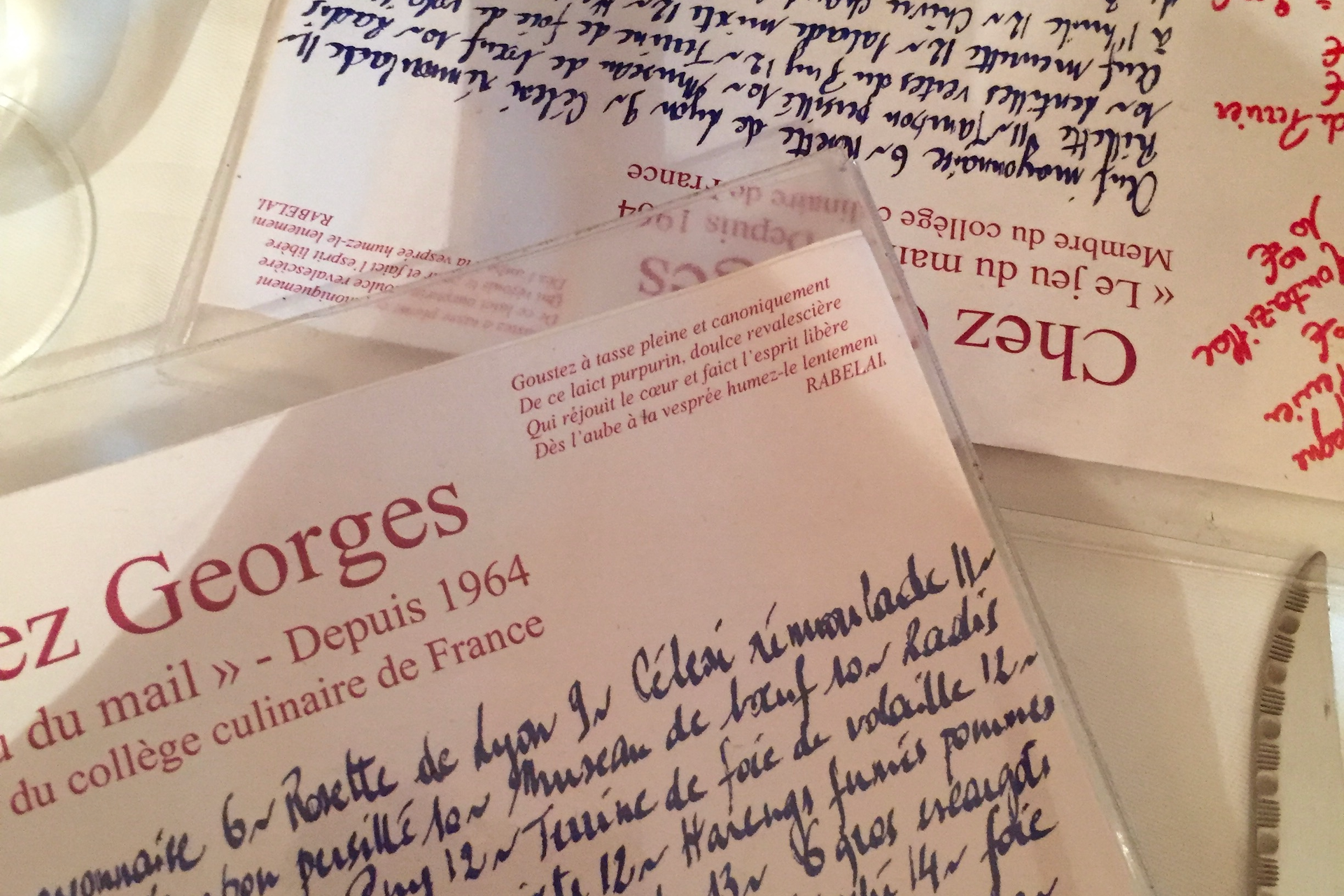生き方に影響を与えてくれた作家
本という存在が、衣食住とほとんど同義になったのは、いつの頃からだっただろう。
思い返すのも困難であるくらい、読書が日常になっている幸福を、日々感じています。
本に書かれてあるのは人の言葉、人の思い、人の生きる時間です。書かれてあることと向き合っている時間、私たちは、作者や登場人物のまなざしを借りて世界をみつめます。
そんなふうにして、感覚の確認作業と発見作業を繰り返しながら、世間を、人を、そして自分自身を知っていく。そう考えると、一冊の本と巡り合うとは人との出会いと同等で、相性やタイミング次第では、その後の生き方や価値基準をも大きく変える力をも、本は持っていると思うのです。
私にとって人生に大きな影響を与えてくれた作家のひとりに、角田光代さんがいます。
10代の頃から、角田さんの書くものを読んできました。
「ふつう」が分からず、できず、大人を困らせていた子どもの頃の記憶を癒やしてくれたのも。好きな人にこっぴどくふられて自堕落な生活から抜けられなくなった時期に寄り添ってくれたのも。バックパッカーの旅に目覚めさせてくれたのも、旅先で眠れぬ夜を共に過ごしてくれたのも。書くことを仕事にしようと決めたときも、女性という性の前に差し出される人生の選択に悩んだときも、角田作品を読んで生きてきました。
読んだからそういう人間になったのか、あるいは、もともとあった性分を角田さんが言語化してくれたのか。どちらが先だったのか、もはや曖昧になっていることさえあるほどに、角田作品を読むことと、実人生を生きることは繋がっています。
当たり前にしていたことが、ある日突然できなくなった
本という存在は衣食住とほとんど同義。
そう思っていたし、実際そういう生活を送っていたのですが、実は少し前、突然本が読めなくなるという経験をしました。文字を目で追い続けても、なぜなのかいつものように言葉が入ってこない。物語の世界がぱっとひらかれるあの感覚を思い出そうとしても、現実で抱えている問題に心が引き止められてしまって、集中できない。
本を読むことは仕事でもあるのだから、しっかりしなくちゃ。そんなふうに自分を律しても逆効果で、無理に読もうとすればするほどに、かえって読めなくなっていくばかり。
こんな経験は初めてでした。
不思議なもので、本が読めなくなると、食べることや眠ることにまで影響が及んでいきました。
人と囲む食卓はもちろん、自分のために作って食べるというつましくも静謐なひとときも、かけがえのない日常の一部であったはずなのに、適当にコンビニで済ませてしまったり、気づけば夜まで何も口にしていなかったりと、なんだかもう、どうでもいいやという気分。
次に来たのは睡眠障害でした。
たいして仕事もしていないから眠くならないのは当然で、こんな日々がいつまで続くのかという不安や遅い時間の暴食が、自律神経を乱してしまって、鬱々とした気持ちは増すばかり。本を読むことが日常から欠けてしまっただけで、ここまでダメになっていくのかと打ちひしがれつつも、無為に日々を過ごすしかありませんでした。
また始めるために、指をかけていた一冊
それはほとんど反射運動だったのだと、いま振り返って思います。
気分転換に街歩きでもしてみようと思い立ち、下北沢を訪れてはみたものの、行くあてを早々になくした私が逃げ込むように入っていたのは、そんなふうにまでなってなお本屋でした。
ぼんやりしたまま棚に並ぶ本の背を眺めていると、指がある一冊をめがけて動いたのです。
タイトルは、『ゆうべの食卓』。
著者名は、角田光代。

知らないうちに新刊が出ていたことに反応したというのは、あったと思います。けれどそのとき、「角田光代」という四字が、おおげさではなく光って見えた。その光に縋るように、吸い寄せられるように、指をかけていたのです。
11の物語が詰まった「ゆうべの食卓」
『ゆうべの食卓』と題された11編の物語には、変化を恐れず、むしろ楽しもうとする人々の姿が、いくつもの食卓の風景とともに描かれていました。
コロナによる家庭内別居を経て離婚、“ユニット”という新しい家族のかたちを見出す「パパ飯ママ飯」。初恋を経験してどんどん大人びていく友だちと、もう少し子どものままでいたい女の子の友情が愛おしい「それぞれの夢」。45年住んだ実家の取り壊しをきっかけに、家族で囲んだ食卓の記憶が蘇る「私たちのちいさな歴史」……。
変わっていく関係や、叶わないこともある現実や、失ってもなお続いていく日々を生きるのが人生だ。
複雑でままならない事情を抱えていても、私たちは、ごはんを食べて生きていく。
ごはんを食べておいしいと思えれば、あなたもきっと大丈夫。
そんな声が本の中から聞こえてくるような、優しくもたくましい短編集でした。
本を読んでいる。本を読めている。
そんなことに意識が向くまもないほどに、本の世界にすっと入っていけたのだから不思議でした。
わたしの素
自分を大丈夫にしてくれた「だいじょうぶ野菜」
久しぶりにキッチンに立った、日曜日の昼。また本が読めるようになったからといって、それは角田さんの本だからだったのかもしれないし、停滞させてしまった仕事のしわ寄せはこの先やってくるのだし、不安が消えたわけではない。でも、ごはんを食べよう。自分のために、作って食べよう。そう思うことができたのです。
定番のお昼メニューのひとつ、とろろそばを作る直前にひらめいてスーパーに走ったのは、「大丈夫」のもうひと声が欲しかったから。
「398円!?」と一瞬ひるむも、強い気持ちで一袋をもとめ、蕎麦と一緒にお鍋で茹でたのは、ほうれん草でした。以前、角田さんがエッセイで、〈「あれを食べればだいじょうぶ」と思う野菜って、ないですか?〉という問いかけから、自らの「だいじょうぶ野菜」としてほうれん草をあげていたことを思い出したからです。
──ほうれん草を食べさえすれば、私もだいじょうぶな気がする。
傍目に見れば、茹でたほうれん草を蕎麦に乗せただけのこと。でも、その一手間をかけてみようと思い立ち、実際に行動できた。そのことが、とても嬉しかったのです。 
人が日常を取り戻すきっかけは、これくらいささやかなところにあるのかもしれない。そんなことに、はたと気づきます。気晴らしに旅行をしてみるとか、ちょっと豪華な食事に出かけてみるとか、非日常に身を置いてみるのも手かもしれないけれど、どうやら私は、そういうタイプじゃないらしい。私が私を取り戻すには、やっぱり言葉が必要で、人生の一部にもなっている角田さんの言葉が、今回私を救ってくれた。
「だいじょうぶ野菜」の入った蕎麦を汁まで飲み切ったとき、自然に口からこぼれていた「おいしかった〜!」のひとことが、再生につながる確かな手応えを、私に与えてくれたのでした。
私のおいしさの扉
「だいじょうぶ野菜入り月見とろろ蕎麦」