
オイシサノトビラ
菅原敏
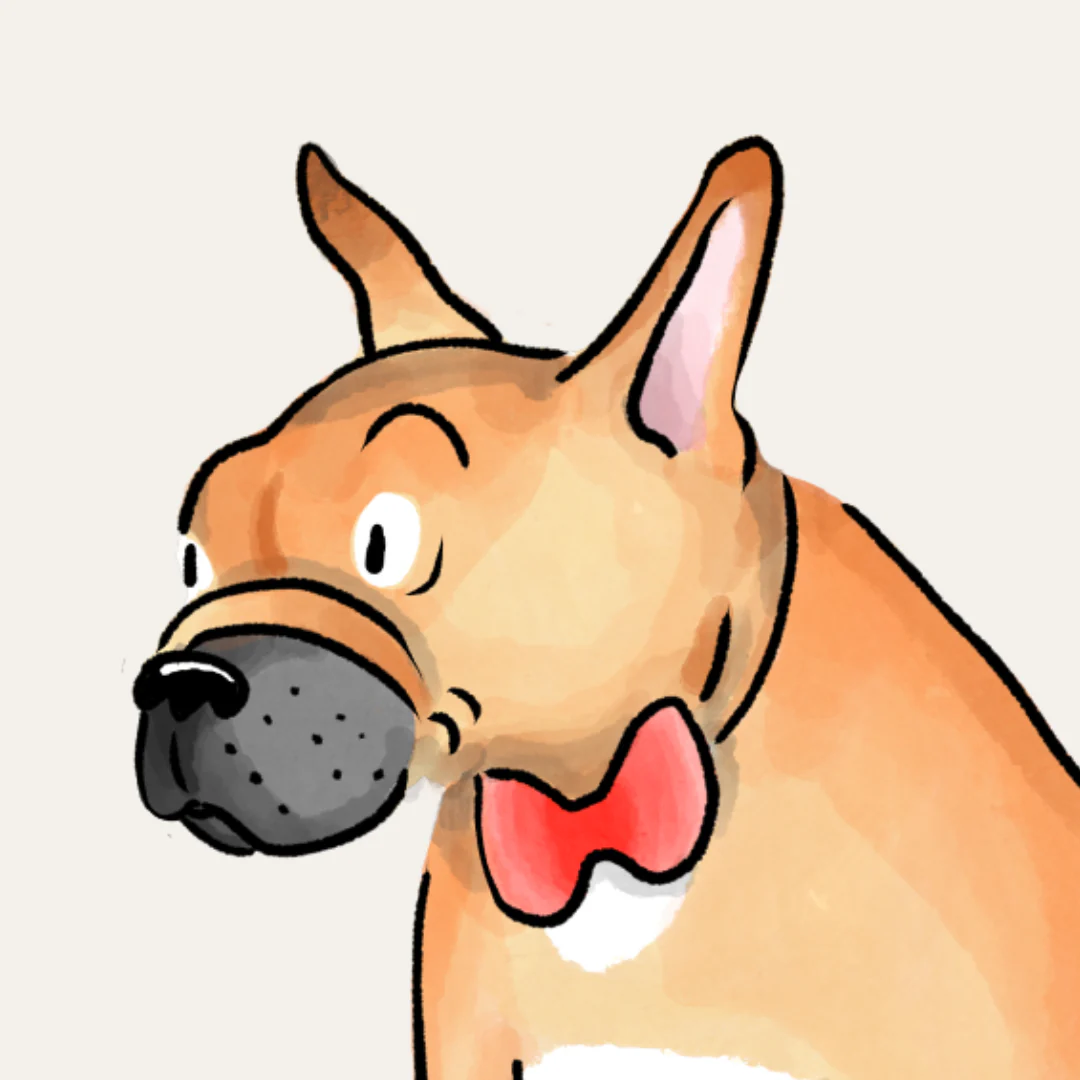
オイシサノトビラ
──── 前編は、詩人 菅原敏さんが詩に関心を寄せるようになったきっかけと、表現のスタンスを伺った。食べることと詩を読むことって、どこか似ている気がする、と菅原さん。両方に真摯に向き合ってきた彼だからこそ、気づいたことがある。
「食の世界って、お皿の上に広がる風景からも、舌の上で味わうことからも、どこか未知の場所へと連れていかれる感覚があると思っています。詩もそれに似ていて。例えば、小説には結末という目的地が決まっているけれど、多分に余白のある詩は、その時々によってどこに連れて行かれるか分からない。行き先が見えない面白さこそ、両者に共通することだと思いますね」
そんな彼が折に触れて足を運ぶのが、横浜・関内にある〈イサベラ〉。創業は1969年、一晩一組限定というスタイルのスペイン料理店だ。
「お店の二代目オーナーである茶人の松村宗亮さんと親しくしている縁で、10年以上前に訪れたのが最初です。料理とともに、家とも友人の家とも違う、けれどもどこかほっとする落ち着いた空間に心惹かれたことを覚えています」

今では気の置けない友人たちとともに、季節ごとの句読点を打ちにいく感覚で訪れている、と菅原さん。その言葉の通り、提供される季節のコース料理はどれも、日本全国から仕入れた旬の食材をふんだんに使い、モダンで繊細な仕上がり。口に運びながら、シェフの西村優作さんと交わす会話もまた、楽しみのひとつだ。
「ほうぼうから新鮮な魚介類を仕入れていて、西村さんはいつもその裏側をお話ししてくださいます。スペインはもちろん、いろんな海へと思いを馳せられるのも嬉しいところですね」
岡本太郎の花器やピカソの壺、現代アートまで、多彩なコレクションがちりばめられたコンパクトな店内では、遊び心あふれる気遣いも。
「コースを一通り終えると、ある封筒が手渡されます。入っているのは、先代オーナーに開業のきっかけを与えたとされる『マダム イサベラ』からの直筆のお手紙と、彼女が撮ったであろうかつての横浜の写真です。通うたびに、在りし日の横浜の姿とマダムの半生が垣間見えて、時間が巻き戻っていく感覚になる。そんな物語に身を委ねるのも、このお店の醍醐味です」

こんなふうに、食材や店の背景にある物語とともに、目の前の食を舌の上で、そして心で味わい尽くす菅原さん。その記憶の原点には、幼い頃に母がよく作ってくれたデザートがある。
「苺の季節に、よく母が苺ソースのブラン・マンジェを作ってくれました。冷蔵庫のなかに、銀の器に入った完成間近のブラン・マンジェが並ぶ光景にいつもワクワクしていたんですが、たった一度、その状態で母が3日ほどいなくなったことがあって。今思えば父と喧嘩でもして、実家に帰っていたのだと思いますが、子供心に強烈に刻まれたのが、冷蔵庫のなかの赤と白、そして母の不在。母を亡くした今も、不意に思い出すのはそのことばかり。私にとって食のおいしさは、それを取り巻く時間の尊さとともに心に刻まれるものなのだと思います」
わたしの素

「使い切っては買って、を繰り返しているのが、フルール・ド・セルというフランスの塩です。最初に手にしたのは数年前。仕事で訪れたパリで、写真家の友人に連れられて日本人のシェフがやっているビストロ〈ル・ソリレス〉に足を運びました。料理も空間も素晴らしく、シェフへの挨拶代わりに自分の詩集をお渡ししたら、お返しにくださったのがこの塩。せいろで蒸した野菜にパラっとかけるだけで味が決まるので、使い切った後にもネットで買って、常備するようになりました。サラダでもお肉でも目玉焼きでも、これをかけておけばどうにかなるだろう! という祈りのような調味料。パッケージも可愛いので、誰かへのちょっとしたプレゼントにもしています」(本人購入品)
profile

菅原敏 / すがわら びん
詩人
2011年に、アメリカの出版社PRE/POSTより詩集『裸でベランダ/ウサギと女たち』で逆輸入デビュー。以降、執筆活動を軸にラジオでの朗読や歌詞提供などで幅広く活動。近著に『季節を脱いで ふたりは潜る』など。最新詩集『珈琲夜船』(雷鳥社)が2024年11月7日に発売。
Credit:FRaU編集部
photo:Ayumi Yamamoto
text & edit:Emi Fukushima
イサベラ
神奈川県横浜市中区翁町1-5-14
☎080-9394-2960
連載
オイシサノトビラの扉
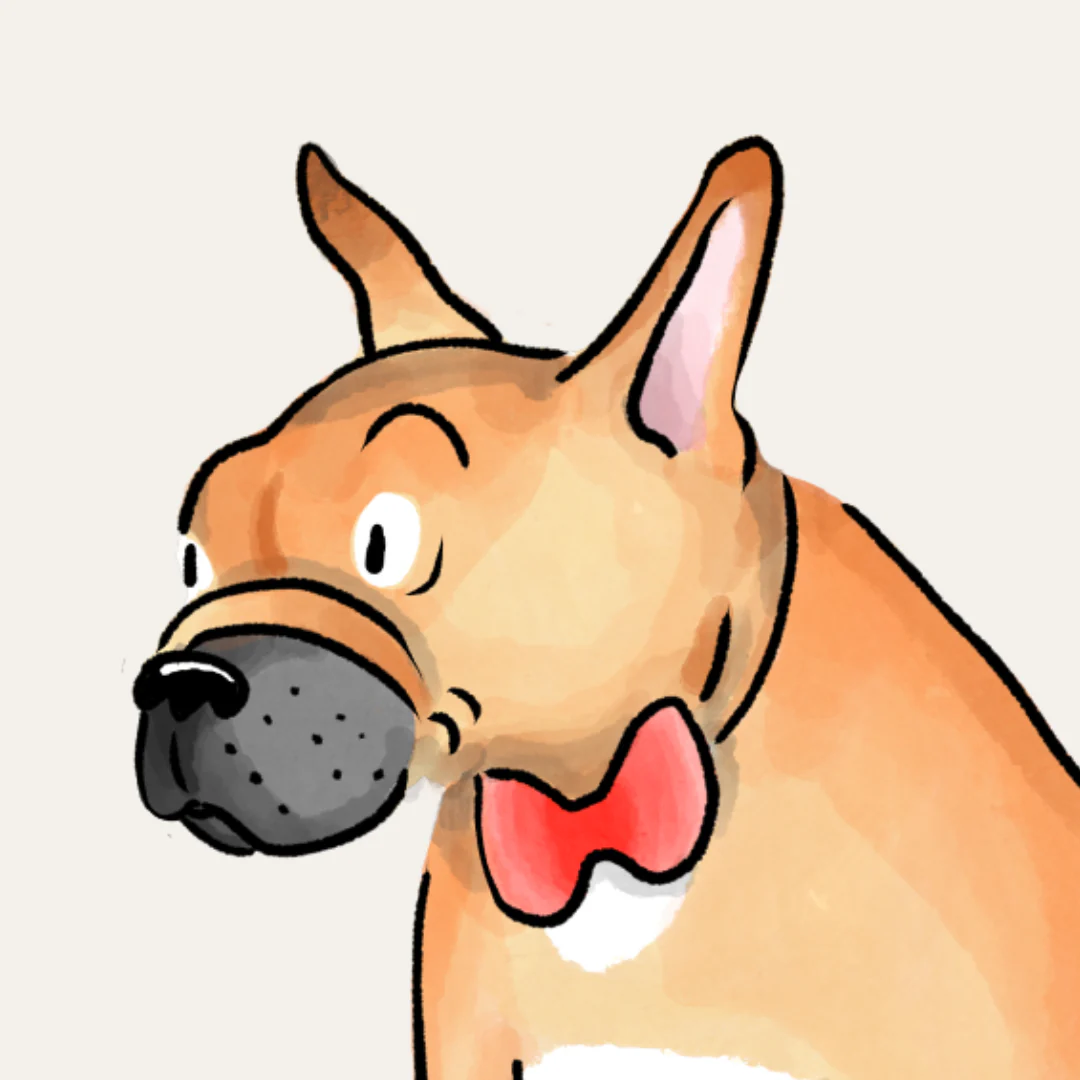
オイシサノトビラ
「おいしさって、なんだろう?」をテーマに、その人の生きる素となるような食事との出合いやきっかけをつくることを目指しています。