
オイシサノトビラ
蒸留家|江口 宏志
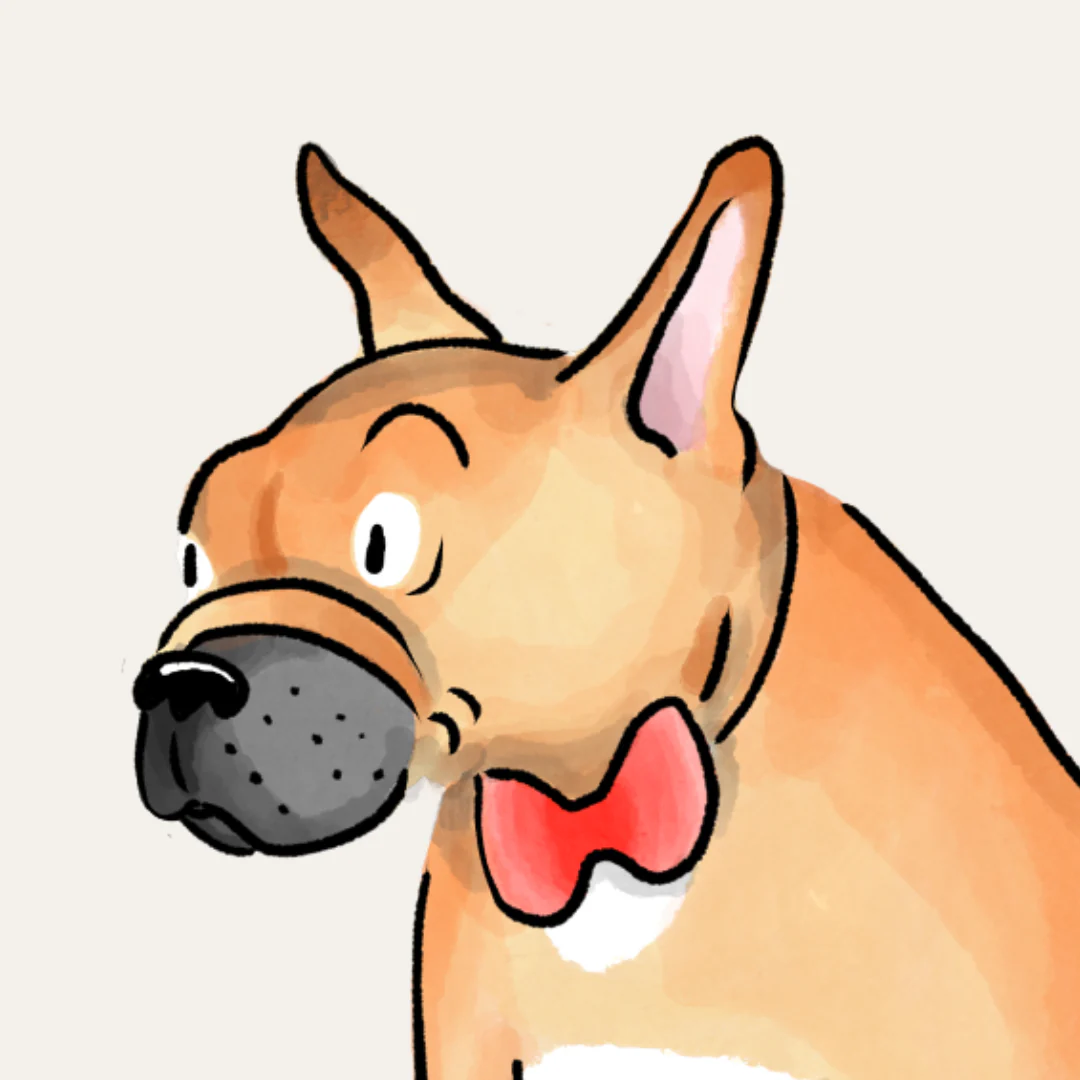
オイシサノトビラ
──── 2017年、千葉県南部の大多喜町にフレッシュな果樹やハーブを素材とした蒸留酒を造る〈mitosaya薬草園蒸留所〉を立ち上げて5年。お邪魔したのは、2023年5月に清澄白河でスタートした、ノンアルコール飲料を小ロットで製造販売する缶のボトリング工場〈CAN-PANY〉。江口宏志さんの仕事は、2000年代初頭に本屋から始まったそのキャリアからは、想像もつかないところにまでたどり着いた。

「お酒に興味を持つきっかけとなったのは、当時通っていた中目黒の美容院〈mitsouko〉の工藤耕成さん。僕より1~2歳上の同世代で、話の合う、センスの良い面白い人。いつも新しいことを教えてくれて、彼からは結構、いろいろな影響を受けているんですよ」と、工藤さんとのエピソードのなかでも印象深い、忘れられない出来事を話してくれた。
「本屋さんだった頃、週に1度、神保町の古書組合へ行く度に〈丸香〉で大盛りのうどんを食べていた。だから、ちょっとぽっちゃりしてきたんです。そしたら一緒に飲みに行った時、『江口くんの仕事は、美しいものやお洒落なものを紹介する仕事だよね。だったらさ……、太ってんじゃねーよ!』と言われたんです。酔いの途中で、その言葉がショックで頭から離れなくて。それ以来、僕は大盛りを止めました(笑)」
〈mitosaya〉につながる酒との出会いは、工藤さんに髪を切ってもらっている最中だった。
「ある日、飲んで欲しいお酒があると、白いケープを付けた状態で、いきなりストレートの蒸留酒を渡された。それまで、そんなお酒の飲み方すら未経験だったのに、飲んだらまるで森の中に佇んでいるかのような香りが立って。お酒でそんな体験って初めてだったので、ものすごく感動して、衝撃を受けた。ボトルを見せてもらったら活版印刷のラベルもカッコ良く、裏にはサインとシリアルナンバーが入っていて、これは本の表紙だよね、という話をしたんです」

その時に飲んだのが、当時まだ日本にほぼ入っていなかったボタニカル・ジン「MONKEY 47」。蒸留酒が香りの酒だと知った衝撃は想像以上で、すぐに蒸留所〈スティーレミューレ〉のことを調べた。代表のクリストフ・ケラーがもともと本の編集の仕事をしていたのも、江口さんの心を酒へと動かした大きな要因となる。
「全く新しい香りの体験とともに、お酒というのがパッケージやラベルや名前といったものを含んだ総合的な表現であり、本の編集に近いのにも親和性を感じました。その後、彼のインタビューに、『 〟本は読むまで中身がわからないけれど、お酒の場合は一口飲めば誰もが味を共有できる』〝とあって。『 〟今までスノッブなアート系の奴らとしか話が合わなかったけれど、隣の農家の人も一口でこれがおいしいか、好きかどうかがわかるのがいい』〝と書いてあった。まだ造ってもいなかったけれど、なるほどそういうことか、それは面白い世界だなと思ったんです」
後編につづく。
profile

江口宏志 / えぐち ひろし
蒸留家 / 1972年、長野県生まれ。
ブックショップ〈UTRECHT〉、「TOKYO ART BOOK FAIR」ディレクターを経て、蒸留家の道へ。果物や植物を用いた蒸留酒を主軸とした〈mitosaya薬草園蒸留所〉、ノンアルコール飲料を製造販売する〈CAN-PANY〉など、丁寧なものづくりに関わる。
Credit:FRaU編集部
photo:Masayuki Nakaya
text & edit:Asuka Ochi
連載
オイシサノトビラの扉
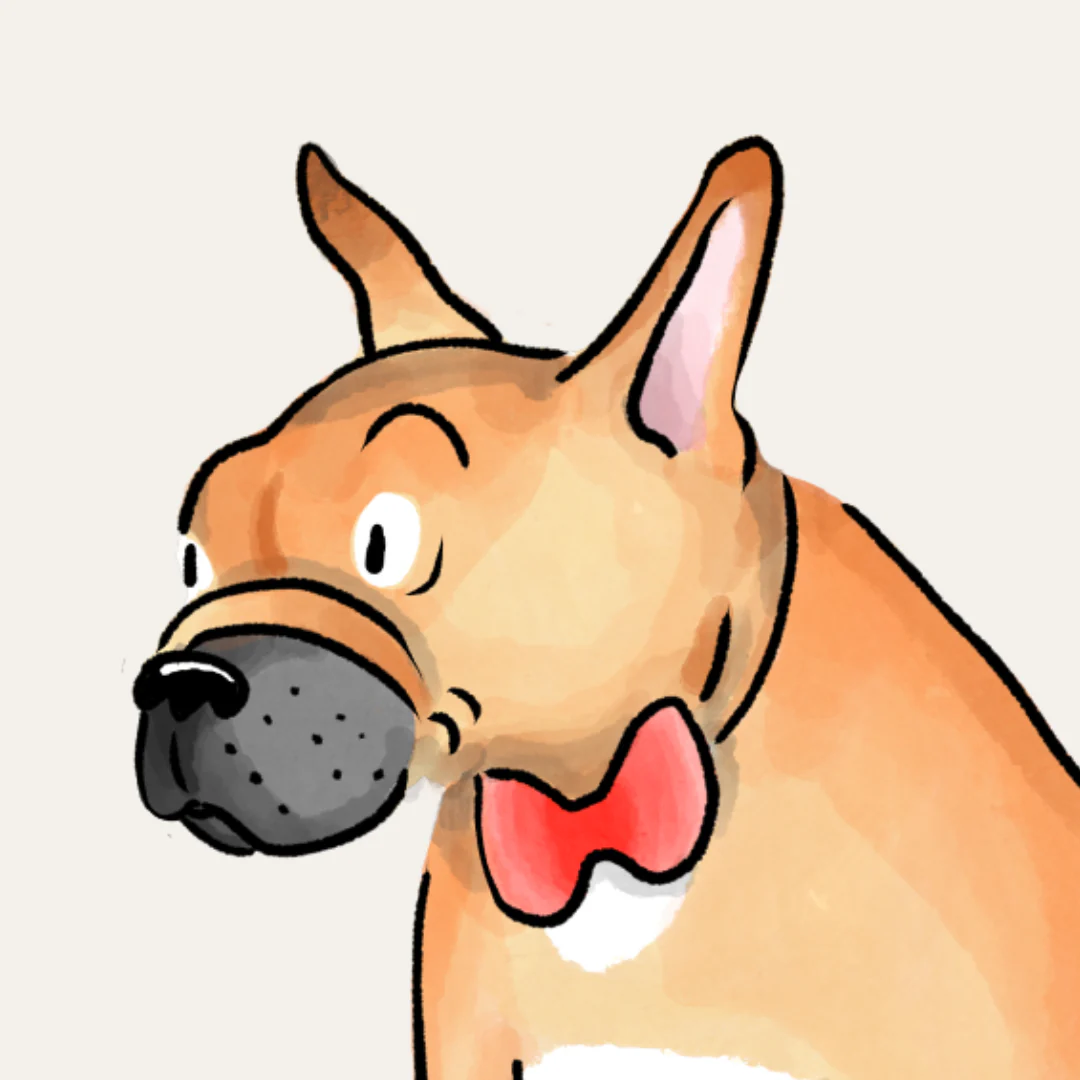
オイシサノトビラ
「おいしさって、なんだろう?」をテーマに、その人の生きる素となるような食事との出合いやきっかけをつくることを目指しています。