
オイシサノトビラ
陶芸家|吉田 直嗣
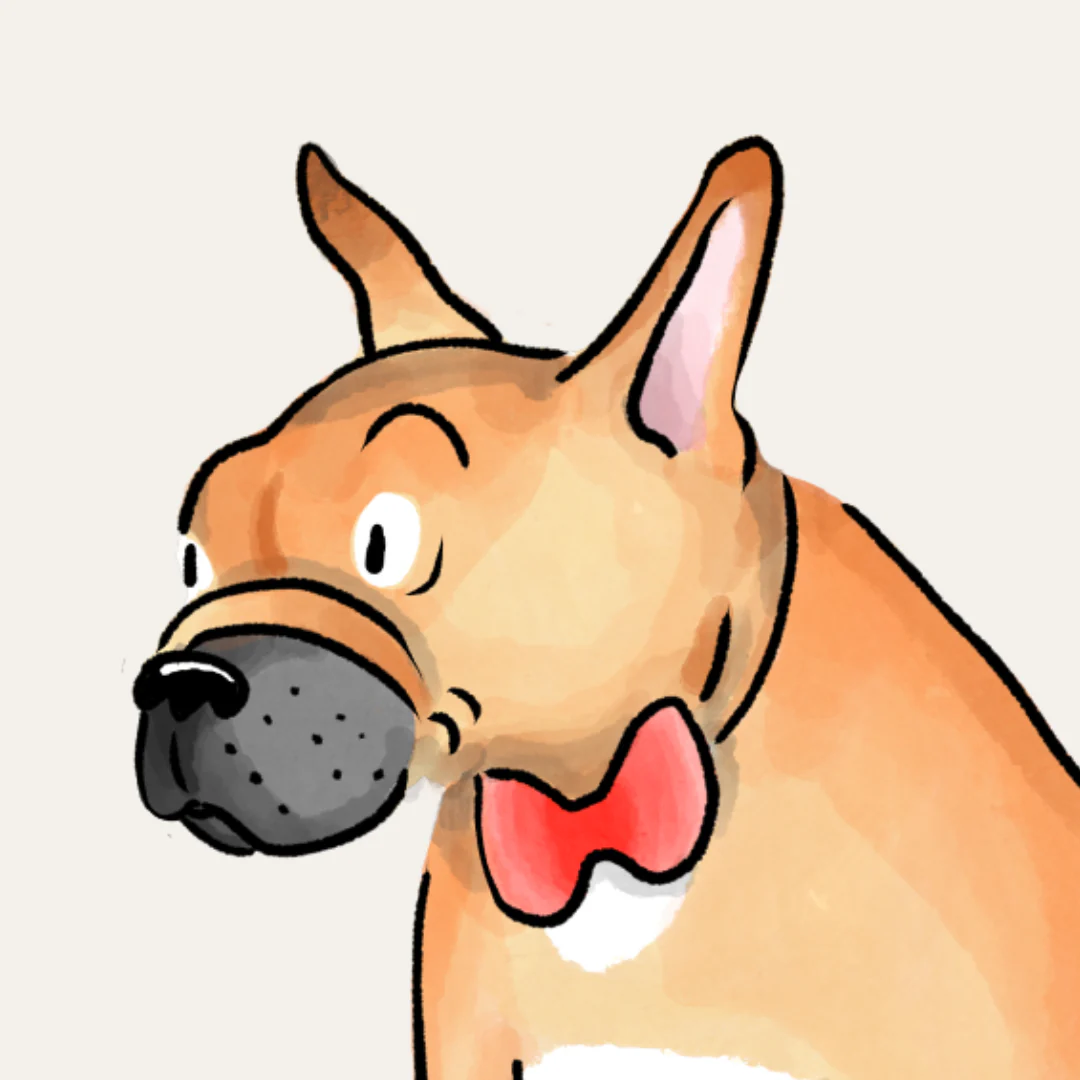
オイシサノトビラ
────静岡県沼津市で生まれ育ち、現在は駿東郡小山町に工房を構える陶芸家の吉田直嗣さん。陶芸家の黒田泰蔵氏に師事し、2003年に独立して以降、モノトーンかつミニマルな意匠で人気を博している。
はたして、吉田さんが手掛ける器にはどのような想いが込められているのか。そして、吉田さんにとっての「美しさ」と「おいしさ」とはどのようなものなのか。
自然に囲まれたご自宅兼工房でインタビューをさせていただくと、気取らず自然体でありながらも思慮深い言葉の数々が返ってきた。

創作への想いとこだわり
オイシサノトビラ
一見するとシンプルなでありながら、奥深さが感じられるのが吉田さんの器の魅力だと思うのですが、吉田さんご自身では普段、どんな器を使っているのでしょうか。
吉田
他人が作った器は「なんでこういう形にしたんだろう」とか「きっとこんな意図でこの形にしたんだろうな」といった気持ちが湧いてきてしまうので、普段は自分が作ったものを使うようにしています。といっても、自宅に残すのは割れ物をはじめとしたB品が大半で、その他は個展などに出すようにしています。
オイシサノトビラ
吉田さんの作品は、ほとんどがモノトーンで形へのこだわりをとても感じます。

吉田
こだわってはいるんですが、僕自身が気まぐれで。その日の気持ちによって作りたいものや形はコロコロと変わるんです。たとえば、僕はしょっちゅうコーヒーを飲むんですが、コーヒーカップを持った時のバランスや重量のかかり方などを調整して、ロジカルに使いやすい形をイメージしながら作っています。ただ、それ以外の器は自分の中の想いをアウトプットすることを重視しているので、その日その日でまったく理想とする形が変わってきてしまう。
オイシサノトビラ
想いをアウトプットするという表現が吉田さんを表しているように感じました。一方で、お客さんや取引先から「こんなものがほしい」といったリクエストを受けることもあるのではないでしょうか。
吉田
関係性のあるギャラリーで展示をさせていただくことが多いので、僕のことを上手に泳がせてくれます。僕ってどこか天邪鬼なところがあって、「カップがほしい」と言われると「皿を作りたい」と思ってしまったりしてしまう。さっき話したようにその時々によって作りたいものや形が変わってしまう。ある程度、自由にさせてもらった方が意欲的に仕事ができるんです。我ながら社会不適合者だなと思ってしまいますが、こればかりはどうにもならないですね。
オイシサノトビラ
ほぼ毎月といっていいほど展示を開催されているとうかがいしました。すごいペースだなと思うのですが、その時のテーマはどのように決めているのですか。
吉田
実は展示に関しても、あらかじめテーマや企画を決めることはほとんどないんです。とにかく器をひとつひとつ焼き上げて、それが溜まったタイミング、月1回くらいのペースで展示を実施しているんです。もちろん、ろくろを回す時には「この間はカップをたくさん作ったから今度は皿を多めにしようかな」とか「こないだは小さいものを多めに作ったから、今度は大きめのモノを多めにしようかな」といったことを考えている。ただ、考えるとしてもその程度。あとは日々の自分の気持ちに従って創作を進めていきます。
自分が欲しいものや作りたいものが明確にある時はその気持ちに従うこともあります。たとえば、ラーメンどんぶりを作った時もそうでした。通常のラーメンどんぶりは直径が19cmなんですが、これだと麺とスープで一杯になってしまって、きれいに具をのせることができなかった。どれだけ探してもしっくりくるものが見当たらなかったので、自作してみたんです。すると、これに共感してくれる人が意外と多くうれしい驚きでした。
陶芸の道へ
オイシサノトビラ
お話をうかがっていて、ご自身の感覚をとても大事にされているように思うのですが、吉田さんは幼少期からモノを作ることが好きだったのでしょうか。
吉田
そうですね…。子どもの頃からインドア派で作ることへの興味が強かったように思います。
当時、流行っていたミニ四駆にしても、周りの友だちのようにどのモーターに交換して早さを競うことよりも、かっこよく改造したり、塗装したりすることにこだわっていたりしました。速さよりも見栄えにこだわっていました。
オイシサノトビラ
作るという興味から、どのようにして陶芸の道を歩むことにつながったのでしょうか。大学の授業で陶芸を学ぶ機会があったなどでしょうか。
吉田
大学は、東京造形大学だったのですが、もともとは椅子づくりがしたくて進学したんです。高校の時にインテリアを意識するようになって、イームズチェアなどに憧れていたのが大きかったのかもしれません。まだゼミにも所属していない1年生の頃から家具の先生のもとに通い詰めて、憧れのイスに座らせてもらったり、名作の話を聞いたりしていたのですが、いざその授業やゼミの内容を知っていくと僕の肌には合いそうになかったんです。
最終的には都市デザインを専攻したんですが、ここで学んだことも僕にとってはスケールが大きすぎて手に負えないなと感じました。
オイシサノトビラ
「手に負えない」を感じたという表現も、吉田さんらしい表現だなと感じます。
吉田
大学在学中に、友人から陶芸サークルを紹介されたのがきっかけなんです。「自分にしっくりくる器がないから作ってみよう」と思って取り組んでみると、これが最高におもしろくて、授業そっちのけでのめり込んでいました。誰にも文句を言われずに、作りたいものを作れるし、小さい窯だったこともあって焼き上がりを自分でコントロールしやすかったこともハマった理由かもしれません。やればやるほど自分の技術の拙さが見えてくるんですが、それでも器作りが楽しかったんです。自分の手の届く範囲のものづくりへの関心はそこで生まれましたね。
オイシサノトビラ
そのまま陶芸の道に進もうと決意されたのでしょうか。
吉田
いえ、大学4年になっても卒業後の進路はまったく考えていませんでした。それを見兼ねた友人が競馬新聞の三行広告に伊豆の陶芸教室の求人が出ていることを見つけて、話半分に僕に教えてくれました。「なんで競馬新聞に陶芸教室の広告が」と興味が湧いて電話してみたところ、アッという間に面接に行くことになり、働くこととなり、そこで観光客の方に陶芸を教えることになったんです。ところがその陶芸教室はとにかく忙しくて。自分の腕を磨くことができずちょっと悶々とした気持ちになっていた時に、学生時代にお世話になっていた方が東京で個展をするということで出かけたところ、「プロになりたいなら、それではダメだ」と一喝されました。それから伊豆在住の作家さんを紹介してくださり、その方がアシスタントを探していた陶芸家の黒田泰蔵さんを紹介してくださいました。
黒田さんは当時、月2回のペースで個展を開いていて、陶芸教室を辞めたらすぐに来てほしいというくらい。結果的に黒田さんのもとで働くようになったのですが、その時はまだ黒田さんのことをよく知りませんでした。でも、働き始めて2日目に倉庫で黒田さんの作品や黒田さんのことが掲載されている雑誌を目の当たりにしてハッとしました。黒田さんは、僕が学生時代に憧れていた作品の作家さんだったんです。もともと作家の人物像よりも、作品のことばかりを気にかけていたので、黒田さんのことに気付きませんでした。黒田さんとその作品が一致した時には、あらためて黒田さんに師事できることに感激し、俄然、やる気になりましたね。
オイシサノトビラ
そのモノを誰が作ったのかということよりも、そのモノへの関心が強かったんですね。それにしてもなかなかない経歴ですね。
吉田
振り返ってお話しすると、流されるがまま、ここまできたような感じですよね。黒田さんのもとでは3年弱はたらかせてもらい、2003年に小山町の富士山麓に自分の工房を立ち上げ、現在に至っています。


創作の哲学
オイシサノトビラ
吉田さんは、作家としてご自身が作った器をこういうふうに使ってほしいとか、こういうふうに感じてほしいと思われることはあるのでしょうか。
吉田
そういう気持ちはないんですよね。最初は作品の用途を伝えた方がいいかなと思ったのですが、結局そうやって伝えた用途は僕の考えや想像の範疇でしかないと気付いたんです。器を手に取ってくれるみなさんにお任せした方がおもしろいことが起きるはずだし、僕の想定の何倍も素敵な使い方してくれるはずだと考えています。
美しい器には、どんなものを盛り付けても新たな価値を生み出せる力があると確信しています。たとえば、スーパーやコンビニのお惣菜も美しい器に盛り付ければ、それだけで〝食糧〟から〝料理〟に変わります。このチカラを信じているので、なおのことみなさんの好きなように使ってもらいたいんですよね。
オイシサノトビラ
その「美しさ」はどのように生み出されるのですか。
吉田
ろくろで器を作るという行為は一瞬のきらめきのようなもので、時間を巻き戻して元の形に戻すことはできません。その不可逆性やひとつひとつの違いの中にこそ「美しさ」があると思うんです。ちなみに、展示に同じ形の器を持っていくことはほとんどありません。器には量産タイプの数ものと一点ものがあるわけですが、一点ものしか作らないようにしています。良し悪しは別にして、まったく同じ形の器が並んでいると、僕自身、ちょっと苦しい気持ちになってしまうんです。
オイシサノトビラ
すべての器が、その時その瞬間の吉田さんにしか生み出せない作品なのですね。そうなると愛着が湧いて、手放すのが惜しくなりませんか。
吉田
そうでもなくて、焼き上がった瞬間に満足しちゃうんですよね。それに常に変化を楽しんでいるので、自分が作った器を手元に残しておこうとは思いませんし、いつも明日はもっと良い器ができると思いながら創作に取り組んでいます。あと、在庫があると次の展示が成り立ってしまい、ついついさぼってしまうので、できるだけ早く手放して、急かされるように器作りに励みたい。自分にはまだ伸びしろがあると思っているので、もっと作ってもっとうまくなりたいんですよね。
もっとも、「うまくなる」というのは職人的な技巧のことではありません。職人は、決まった形を同じように作り上げる技巧を磨きますよね。作家は、自分の内面にあるさまざまな想いをより正確にアウトプットすることを目指すんです。作家の方が手先と脳がより近接しているようなイメージという感じでしょうか。僕は自分の内面をアウトプットすることを「圧縮」と表現しているのですが、これは直感的なことのようでいて、その反復によって錬度が上がっていくものでもあるんです。これはある意味、寿司屋の大将の〝仕事〟に近いものかもしれません。寿司を握る数秒の〝仕事〟にはテクニックだけでなく、大将の哲学をはじめとしたさまざまな想いが圧縮されているわけですから。だからこそ、素晴らしい器や寿司には、そのシンプルな見栄え以上の奥深さや味わいがあると考えています。

わたしの素
オイシサノトビラ
器の「美しさ」を追求している吉田さんにとって、「おいしさ」とはどういうものなのでしょうか。
吉田
他の人に自分なりのおいしさを伝えるのって難しいですよね。器に関しても、美しさの基準は人それぞれだし、そう簡単に言語化できるものではありませんしね。きっと「おいしさの基準も同じで、人それぞれ違うと思うんです。ある人は家で食べるごはんがおいしいと言うだろうし、またある人は外で食べるごはんがおいしいと言うでしょう。それに、自分のその時の感情や状況によって、「おいしさ」の基準はかなり変わると思うんです。ワイワイしながら食べるごはんがおいしいと感じる時もあれば、落ち着いて静かに食べるごはんがおいしい感じる時もありますしね。そういう意味では、おいしさも美しさと同じように、自分の内面によるところが大きいものだと思うんです。
オイシサノトビラ
吉田さんご自身はどんな時に、どんなごはんをおいしいと感じますか。
吉田
僕はどちらかというと、味よりも環境を重視するタイプだと思います。だから、外食がとても好きな一方で、家で家族と一緒におしゃべりをしながら食べるごはんがとっても愛おしいし、おいしいと感じるんです。たとえば、朝ごはんを食べながら支度をすませ、「行ってきます」と言って各々が出かけていくようなシチュエーションが大好きで、その時の朝ごはんは日常のちょっとした幸福感に満ちていて、最高においしく感じるんです。
もちろん、この「おいしさ」もその時の感情や状況に応じて、変化していきます。実際、長男が大学に入学して上京してからは、食卓の風景や雰囲気がガラッと変わりましたしね。僕にはもうひとり子どもがいるんですが、彼が大学に進んで家を離れると、今度は夫婦だけになるので、またガラッと食卓の風景や雰囲気が変わり、これまでとは違うおいしさに出合えるようになるかもしれません。これからもいろんな変化があり、いろんなおいしさに出合えると思うと、楽しみで仕方がないですね。

profile

吉田直嗣
1976年生まれ。東京造形大学卒業後、陶芸家黒田泰蔵に師事。2003年富士山麓に築窯、現在では海外にも活躍の場を拡げる。RECTOHALLでは2012年より毎年個展を開催。料理が映えるような潔い黒と白の器が中心で日常づかいにも馴染むデザインが人気を博している。エッジが効いた冴えた印象とおおらかな気配が混在しているのが魅力。
連載
オイシサノトビラの扉
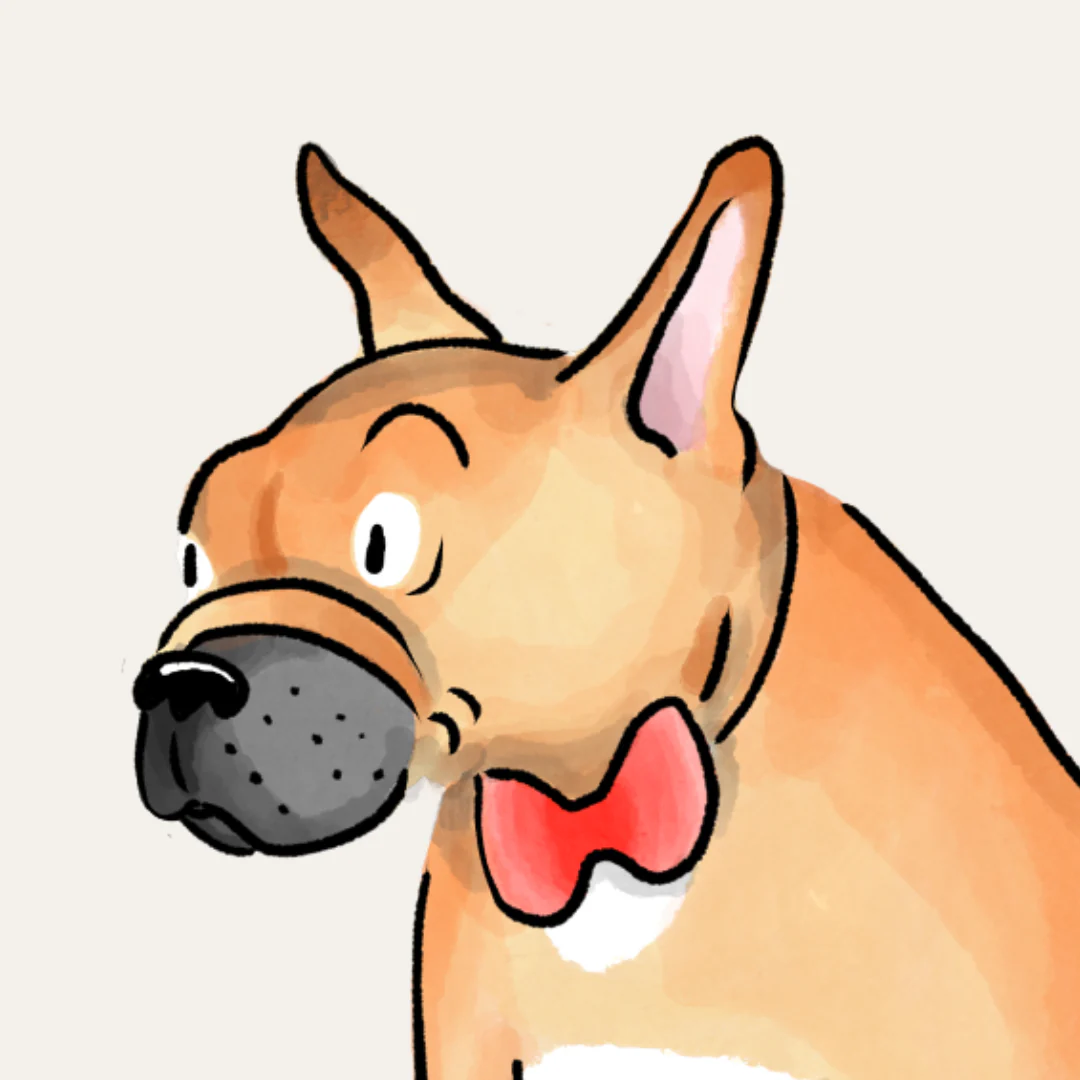
オイシサノトビラ
「おいしさって、なんだろう?」をテーマに、その人の生きる素となるような食事との出合いやきっかけをつくることを目指しています。