
オイシサノトビラ
発明家|ダグラス・ウェバー
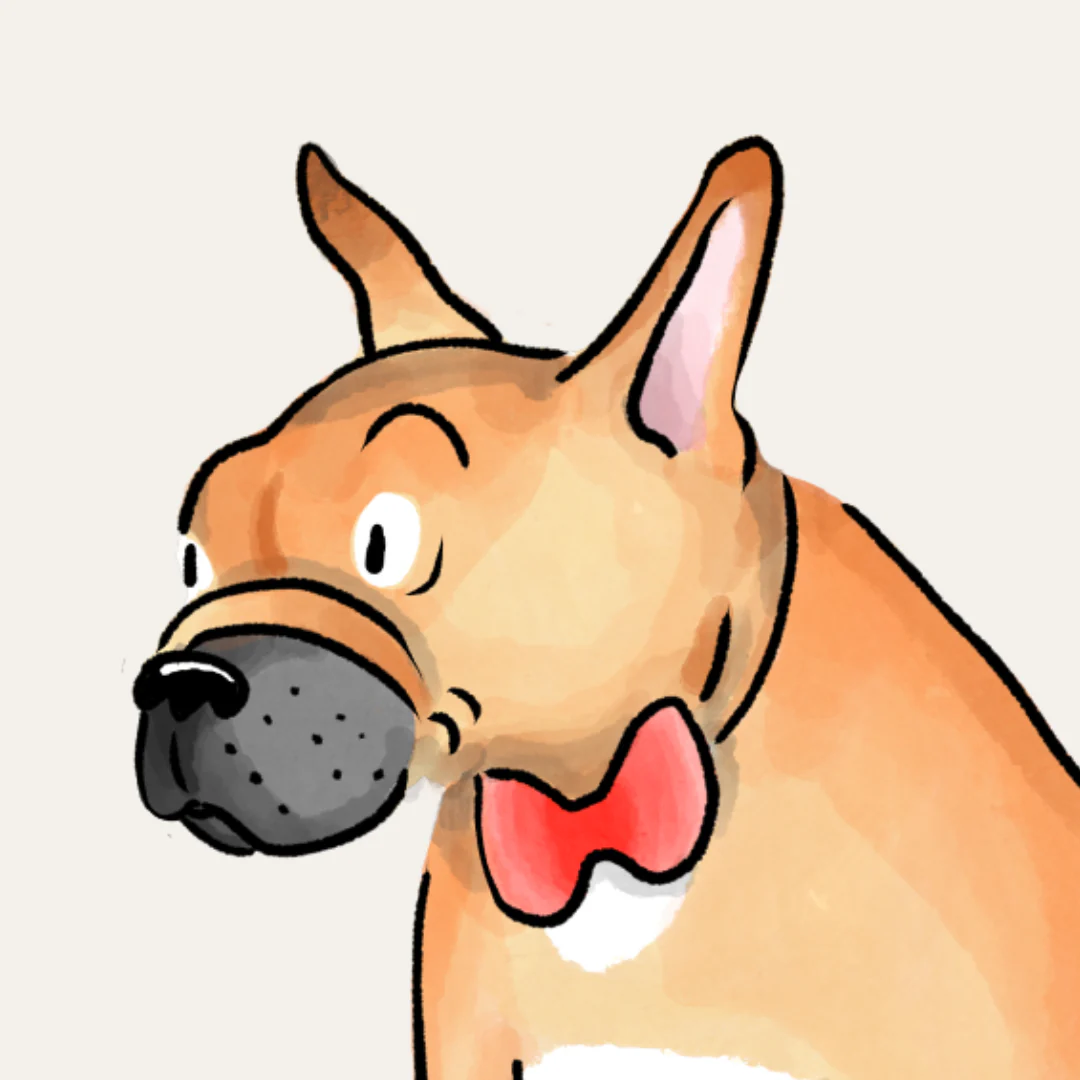
オイシサノトビラ
────元Appleのエンジニアであり、現在は日本でコーヒー器具を開発する「Weber Workshops」のオーナーでもあるダグラス・ウェバーさん。
設計者、プロダクトデザイナー、経営者 …… いくつもの顔を持つダグラスさんに「肩書きってなんですか?」と尋ねると、すこし考えて「今は発明家かな」と返事をしながら「自分で言うのも恥ずかしいけれど。でも数年後には変わるかもしれない」と続けた。発明家...と聞いて、確かにと納得してしまった。その経歴を知り話を聞くほど、しっくりくる肩書きだと思う。
学生時代は陶芸文化に惹かれて日本に留学した。就職先はAppleを選び独立して再び日本に。独自のキャリアを築いてきた彼の視点から、日々の生活を豊かにする「おいしさ」について探ります。

オイシサノトビラ
ダグラスさんは、スタンフォード大学で機械工学を学ばれた後、AppleでiPodの開発に携わられたという経歴をお持ちですが、その前には陶芸に情熱を持たれていたと伺っています。
ダグラス
そうです。学生時代に日本文化に興味を持ち、交換留学で京都大学に入りました。さらに九州大学に留学して、陶芸の世界に魅了されました。陶芸家になりたいと願っていましたが、当時はそれだけでは生計を立てるのは難しいと感じていました。
オイシサノトビラ
Appleからのオファーもあったとうかがいました。
ダグラス
陶芸は年を取ってからでもできると思って、一度断念してアメリカに戻り、Appleに入社しました。結果的に、その選択は正しかったと思っています。Appleでの13年間は激務でしたが、短い期間で何十年分もの経験を積むことができました。その経験があったからこそ、今、日本で自分の会社を立ち上げ、活動できています。
オイシサノトビラ
ダグラスさんは現在コーヒー器具を開発していらっしゃいますが、その頃からコーヒー器具への関心があったのでしょうか。

コーヒーの粉のランダム化/均質化のための器具「MOONRAKER」時計製造、天文学、物理学を詰め込んで開発した。
ダグラス
はい。Appleでの仕事は充実していましたが、多忙を極めていました。多忙であればあるほど、仕事の合間のコーヒータイムが大切だと感じていましたね。僕はもともと機械が好きなのですが、コーヒーはマシンをうまく扱うことによって、よりおいしいコーヒーを楽しめることを知りました。マシンとの一体感を自分ならもっと高められるんじゃないかと。入社2年目には、「いつかコーヒー器具をつくりたい」と思っていました。
オイシサノトビラ
その思いが「Weber Workshops」の創業につながったのですね。
ダグラス
当時もコーヒーのプロダクトはいろいろありましたが、もっとよくできると感じていて、いつか自分でつくりたいと思っていました。同僚と「将来一緒にコーヒーグラインダーをつくろうよ」なんて、話していました。それから、2014年に独立し「Weber Workshops」を創業。2017年には家族を連れて福岡県に移住しました。
オイシサノトビラ
ダグラスさんのグラインダーは、「世界一」を目指して設計されていると伺っています。
ダグラス
プロフェッショナルなエンジニアとして「世の中にこれに勝るグラインダーはない」という思いで設計しています。コーヒー豆の味の可能性を最大限に引き出すには、グラインダーの質は豆と同じくらい重要だと思っています。

EG-1は究極の電動ミル。ドリップやフレンチからエスプレッソまで、どの挽き目にも対応できる万能の道具でもある。
オイシサノトビラ
ご自身の肩書きを「プロダクトデザインエンジニア=発明家」とされていますが、デザイナーであり、設計士でもあるというスタイルはいつ頃から生まれたものなのでしょうか。
ダグラス
元々、工学部出身で設計が専門でしたが、Apple時代にはデザインを考えながら設計するスタイルでやっていました。デザインをする人と設計する人が別だとうまくいかないと感じていたんです。だから、プロダクトをつくる上では、デザインセンスを持つ設計士、あるいは設計もできるデザイナーが一番理想だと考えています。
オイシサノトビラ
そのスタイルで、今や特許取得数は100件以上とのこと。まさに「発明家」ですね。

豆を計量して貯蔵できるビーンセラーはダグラスさんのアイデア。今や世界中に広まっている。
ダグラス
最近は、自分のデザインを理解してくれる設計士を育てながら、自分は発明の方に集中して、次の突破口を開くことにフォーカスしています。
ものづくりにおいて、没頭することは本当に大切です。時間を忘れて何かに打ち込み、気づいたら夜中になっているときもあります。短期的に見れば健康に良くないかもしれませんが、長期的に見れば、それが生きがいになりますから。
オイシサノトビラ
その「没頭」の先にあるものが、充実した人生だと。
ダグラス
生きがいに出逢えない人生を送るのは、何よりもったいないこと。人生において最も大切なものは時間です。時間だけは、お金では置き換えられない有限な資源ですから。

オイシサノトビラ
私たちは、味だけではない「おいしさ」を探求しています。ダグラスさんにとっての「おいしさ」とは何でしょうか。
ダグラス
それは「発見」ですね。誰かが「おいしい」と言っている、星付きの世界もいいと思いますが、自分の「おいしさ」を考えるとあまり魅力を感じません。
オイシサノトビラ
他人の評価ではなく、ご自身の体験を重視されるのですね。
ダグラス
はい。 僕は行列のできる店に並ぶのも、高級店のかしこまった雰囲気も苦手で、そういったものは食事というよりはエンターテイメントのように考えています。そこには味覚的な面白さがあるかもしれませんが、食の本質的な魅力は別のところにあるような気がするのです。僕の食に対する欲求は、人間同士の付き合いや、手で物を仕上げていくことの大切さ、つまり人間味のある食事にあると思います。
オイシサノトビラ
シェフよりも「料理家」という表現がお好きだと聞きましたが、その人間味を大切にされているからでしょうか。
ダグラス
そうです。家庭料理も好きですし、ちょっと荒削りな部分があっても、そういった手づくりのものが一番心を満たしてくれると感じます。それと、時間軸は食事の一部分でもあると思います。気持ちいい時間と場所は、それだけで食事をおいしくしますね。

「きれいな色ですね」と伝えると「カリフォルニアの空をイメージしたんだ」と教えてくれた。
わたしの素
オイシサノトビラ
ダグラスさんが考える「おいしさ」について知りたいです。ダグラスさんが忘れられない食事や大切にしている食事の記憶について教えてください。
ダグラス
最近で言えば、サワードウ(天然酵母のパン)づくりですね。10年ほど前につくった酵母を使って、庭のピザ窯でパンやピザを焼いています。酵母は「付き合うもの」なんですよ。酵母が喜ぶ状態にすると味も良くなる。それがまたおもしろいところだと思います。
オイシサノトビラ
その酵母を、パン屋さんを開いたご友人に分けられたというお話も伺いました。
ダグラス
そういう「人から人へ伝わっていくストーリー」が好きなんです。海外では、パン屋が酵母を分け合うのは当然のことで、それが巡り巡って自分にも返ってくるという考え方があります。
オイシサノトビラ
その「分かち合う」という行為自体が、ダグラスさんの「おいしさ」を構成しているのですね。
天然酵母の話だけでなく、以前養蜂をされていたというお話も興味深かったです。
ダグラス
養蜂も酵母づくりと似ていて、蜂の巣を分ける「分蜂」も同じような考え方が根付いています。いつか自分のがだめになってしまった時にまた分けてもらえるから生業が続けられる。逆も然りで、一種の恩返しの連鎖なんです。
オイシサノトビラ
まさに「オープンソース」の考え方ですね。
ダグラス
そうなんです。日本だと、分蜂した蜂を売ろうとする人もいますが、それは短期的な目線だと思います。僕は、喜んで分けたいと思う。色々な人が持って遊んでくれた方が、蜂自体も喜ぶし、困った時にまた助け合える。特に食に関する分野は、もっとオープンにすることで、みんなが豊かになると信じています。
オイシサノトビラ
ダグラスさんは「コーヒーの世界で貢献できるのは、サービスではなく発明の部分だ」というお話がありました。食の分野でも、その「分かち合い」の精神と「発見」の喜びを広げていきたいという思いがあるのですね。
ダグラス
その通りです。僕がコーヒーの世界に貢献できるのは、サービスではなく、発明の部分だと思っています。だからこそ、自分の得意分野に集中し、そこで得たものを共有していきたいと考えています。

連載
オイシサノトビラの扉
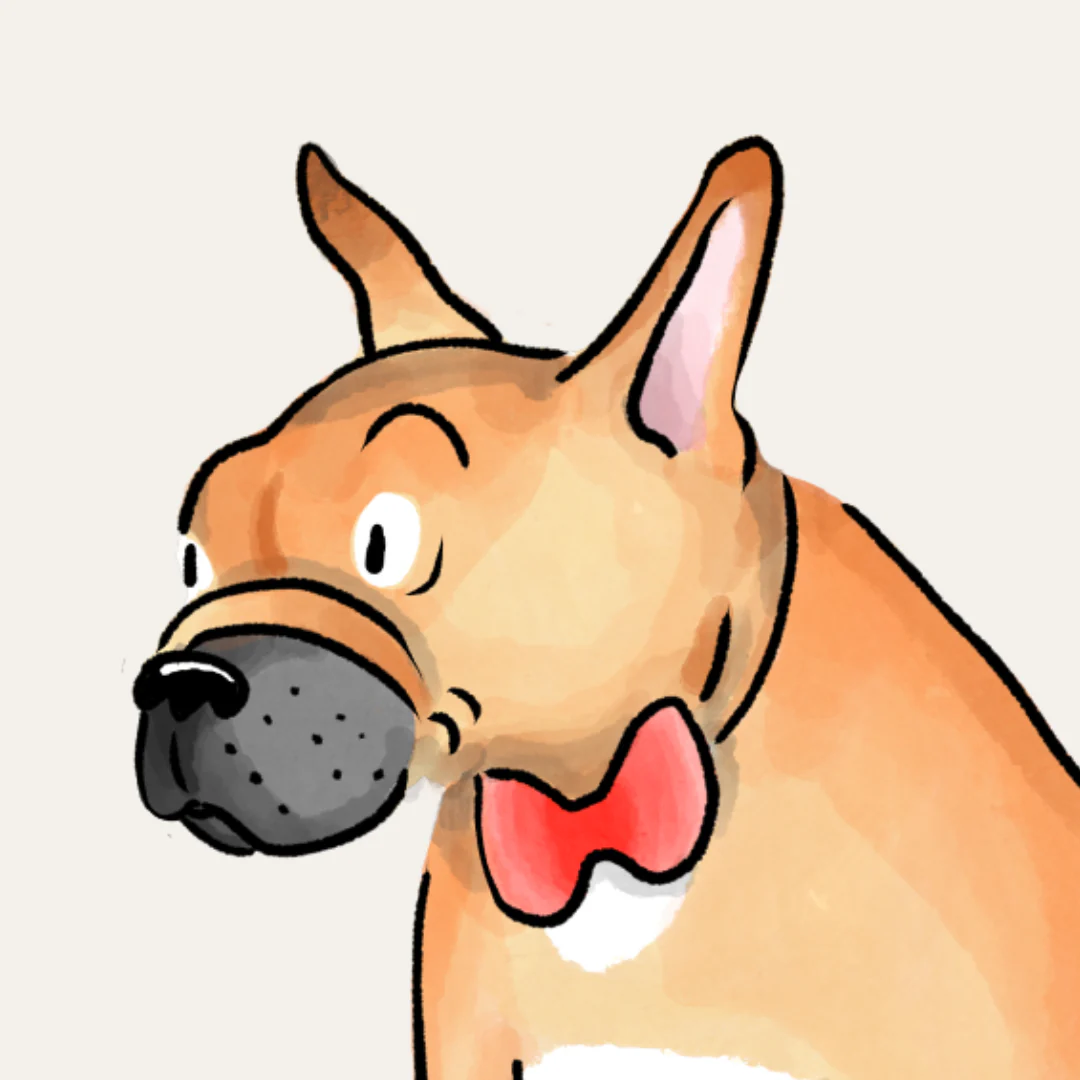
オイシサノトビラ
「おいしさって、なんだろう?」をテーマに、その人の生きる素となるような食事との出合いやきっかけをつくることを目指しています。
.png)



