
オイシサノトビラ
写真家|嶌村 吉祥丸
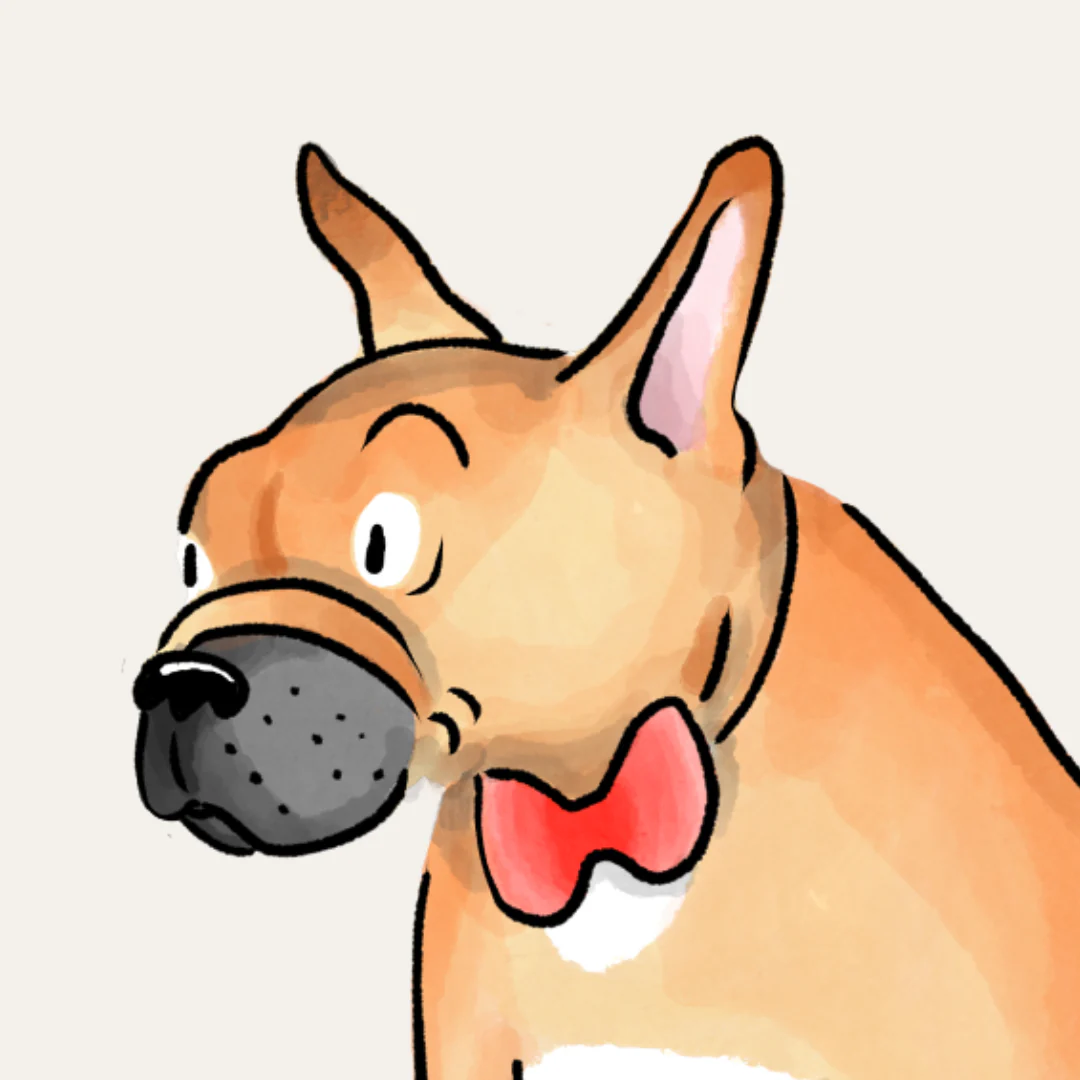
オイシサノトビラ
前編のつづき
オイシサノトビラ
写真業がプロジェクトに影響したり、活かされていたりすることはありますか?
嶌村吉祥丸
ぼくは言語のコミュニケーションを得意だとは言えないのですが、写真を通じてコミュニケーションを取ることは心地良いと思っています。一方でスナックをやっていた期間に養われた視点が写真業に生かされることもありました。たとえば「ここにいる人がちょっと話したいと思っていそうだな」「こっちにいる人とあっちにいる人をつなげたらおもしろくなりそうだな」など、自分中心ではなく空間を俯瞰して捉えることが自然と身につきました。このことは写真を撮る時にも、自分が被写体の側のみを見るのではなく、被写体の人から見える景色を整理すること。どこに誰が立っていたらその場にいる人が居心地良いか。そういうところに気を配って撮影する場づくりをしています。このような感覚はいろいろな活動を通じて、徐々に培われた感覚なのだと思います。それぞれ行なっている活動も、ご縁とモノゴトの流れというのでしょうか、人やものとの出会いから自然に発生していったような感覚なのです。
オイシサノトビラ
お話をうかがっていると、作品やプロジェクトを通じてどのように人や社会とつながることができるのか、ということを考えていらっしゃるのかなという印象をもちました。
嶌村吉祥丸
ありがとうございます。でもそう言われると「ぼくはそんなに人や社会とつながりたいのかな?」 と思ったりもします。つながるというよりは、人や社会に自らを媒介としながら、自然な流れに身を任せている感覚が近いのかもしれません。
ぼくは、自分にとって身近に感じる人にとって、もちろんそうでない人にとっても、居心地が良いと感じる場や機会をひとつでも多く持ってほしい、そしてその選択肢に自分の作っている場やプロジェクトが入ることができたら嬉しいです。
ぼく自身は、場を形成し、運営していくこと自体を楽しんでいますが、プロジェクト単体では経済的に運営を続けていくことが難しい場面もあります。それでも、すべてが資本主義をベースとした場だったらつまらないと思いませんか。そう言った意味で、ビジネスを否定するわけではありませんが、違った選択肢があってもいいと思っています。その上で、純度を高く保っていたいと考えています。
オイシサノトビラ
「純度」が高いということは、どういった状態のことなのでしょうか。
嶌村吉祥丸
物理的にも概念的にも制約が少ない状態のことを「純度が高い」と考えることができるのではないでしょうか。特に東京は経済的な価値観のもとで動かざるを得ないことが多いですよね。一方で、本来人間として純度を持ってあなたはどう生きていきたいですか?と。自分は東京という街で生きているからこそ、そのような普遍的なことを問いかけるような投げかけるような役割でありたいですね。「おいしい」とか、「ちょっとした幸せ」といったご飯を食べるときの豊かさのような、小さな幸せを繰り返していくことが、巡り巡ってこの社会を少しずつでも豊かで良い方向に向かっていくことにつながってゆくのかもしれません。小さな気づきやきっかけがつながり、小さな幸せが連鎖していくことがぼくの小さな願いです。不完全な人間だからこそ、今まで生きてきた中で出会った人たちに教えてもらったことを含めて、いま考えていることを問いかけられる存在の一人になれたらと考えています。


わたしの素
オイシサノトビラ
「ご飯を食べるときの豊かさのような、小さな幸せを繰り返していく」というお話がありましたが、吉祥丸さんが食事で大事にしていることはありますか。
嶌村吉祥丸
日常の中で食べるものは、基本的に自分が住んでるエリアのご飯屋さんに行ったり、たまに自炊することもあります。近所に選択肢がいくつかある中で、気分に合わせてお店を選んで、馴染みの店員さんと話したりできるようなお店に行くことが多いかもしれません。ご飯を食べに行くことも目的ではあるけれど、「最近どう?」といった他愛もないコミュニケーションもふくめた居心地は、食べ物以上に大事にしているかもしれませんね。
オイシサノトビラ
人との出会いやつながりを大切にしている吉祥丸さんならではの「おいしい記憶」について聞かせてもらえますか。
嶌村吉祥丸
今回こういった機会をいただいて考えていたのですが、意外とあるようで思いつかないですね・・・。もちろん実家で食べたご飯も記憶にはありますが、そういうものよりも自分の記憶として色濃いなと思うのは、父が連れて行ってくれたラーメンの記憶です。
小学生の頃サッカークラブに通っていて、試合の時には父親が迎えにきてくれていたのですが、その帰り道にたまにラーメンニ郎に寄っていました。当時は今よりも混んでいなくて、父親のラーメンを分けてもらって食べていましたね。小学校低学年から通って、まだそんなにご飯を食べられなかったのが、小4のある日頑張って完食することができたんです。
はじめて一人前を完食できたときに、少しだけ大人になったと思えたときの記憶が残っています。

profile

嶌村 吉祥丸 | Kisshomaru Shimamura
東京生まれ。アーティスト・写真家として、分野を越境し国内外を問わず活動。さまざまな表現者と協働しながらsame gallery (東京)やkoen(京都)のディレクターとして企画・キュレーションを行うほか、「ラーメン吉祥丸」やフレグランスブランド「kibn」をプロデュース。主な個展に"Unusual Usual"(Portland, 2014)、 “Inside Out” (Warsaw, 2016)、"photosynthesis"(Tokyo, 2020)など。
連載
オイシサノトビラの扉
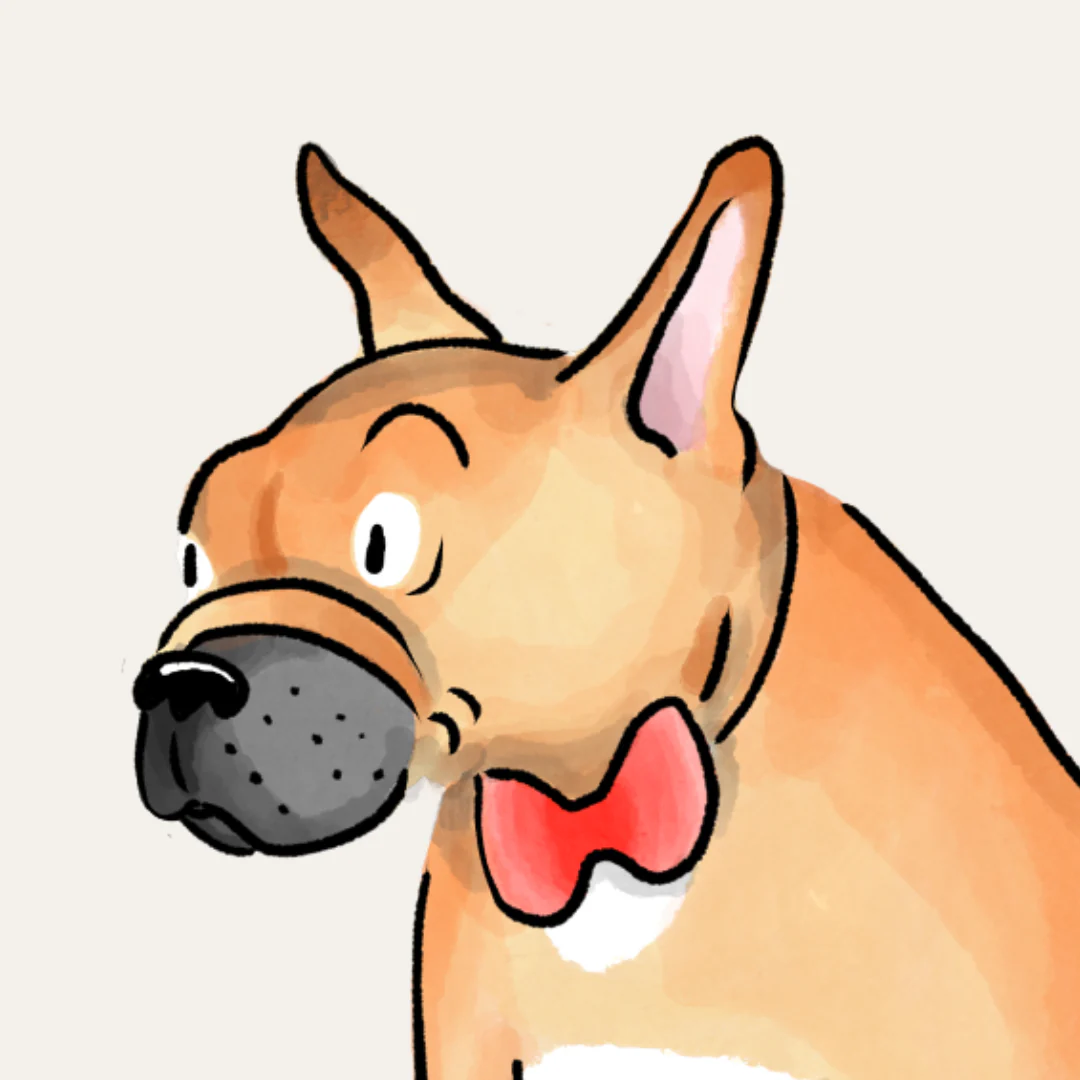
オイシサノトビラ
「おいしさって、なんだろう?」をテーマに、その人の生きる素となるような食事との出合いやきっかけをつくることを目指しています。



