
オイシサノトビラ
精神科医|星野 概念
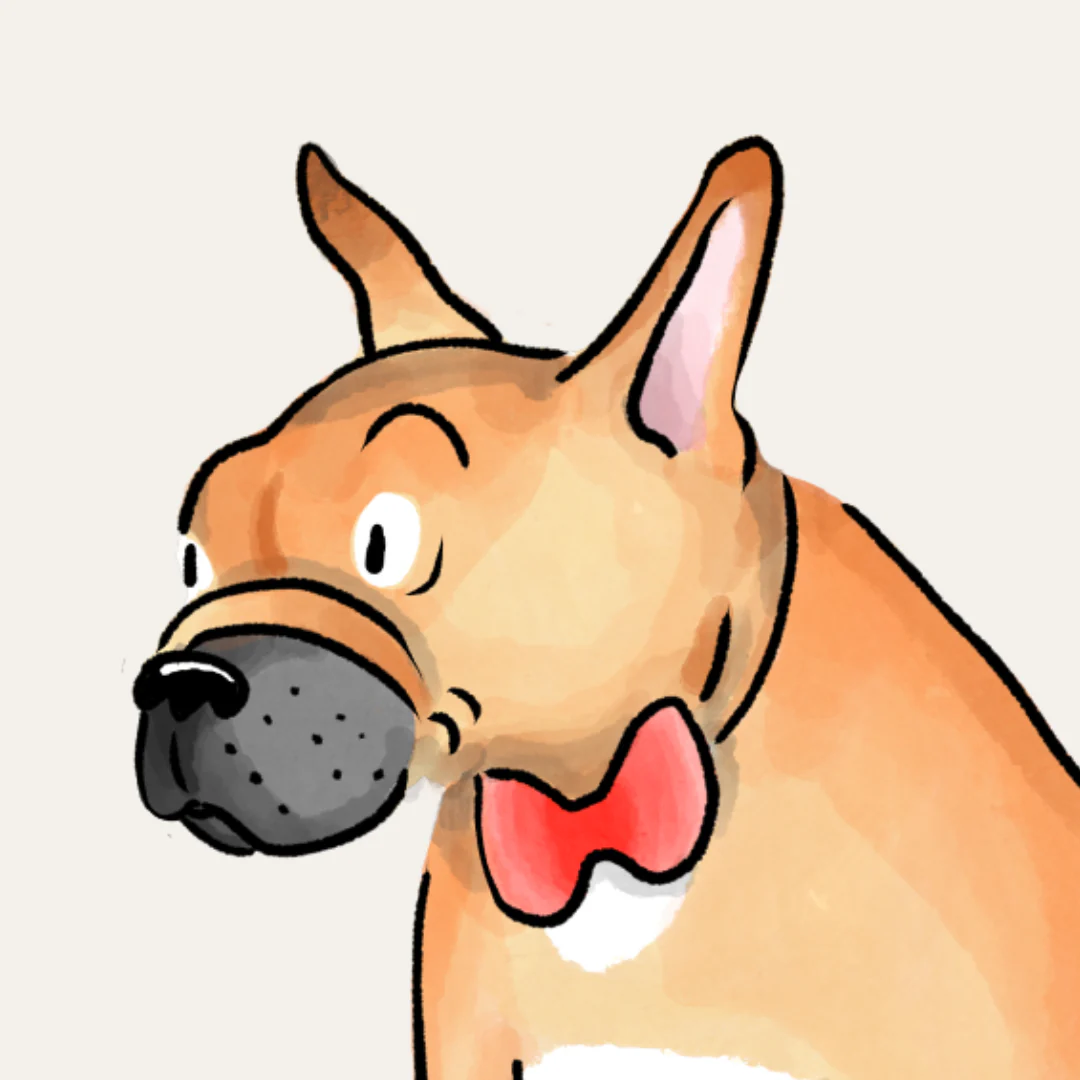
オイシサノトビラ
────精神科医として働きながら、執筆や音楽活動、イベントなどを通し、病院の外でも伝えることを続けている星野概念さん。彼の言葉で、日本ではハードルの高い精神医療を身近に感じ、つらさを感じる時には病院に行ってもいいんだと、背中を押された人は少なくないのではないか。星野さんが、いわゆる教科書通りの診断学に基づく治療と別軸にある、大切なことへの気づきを得たのは医療者として診療を始めた頃だった。
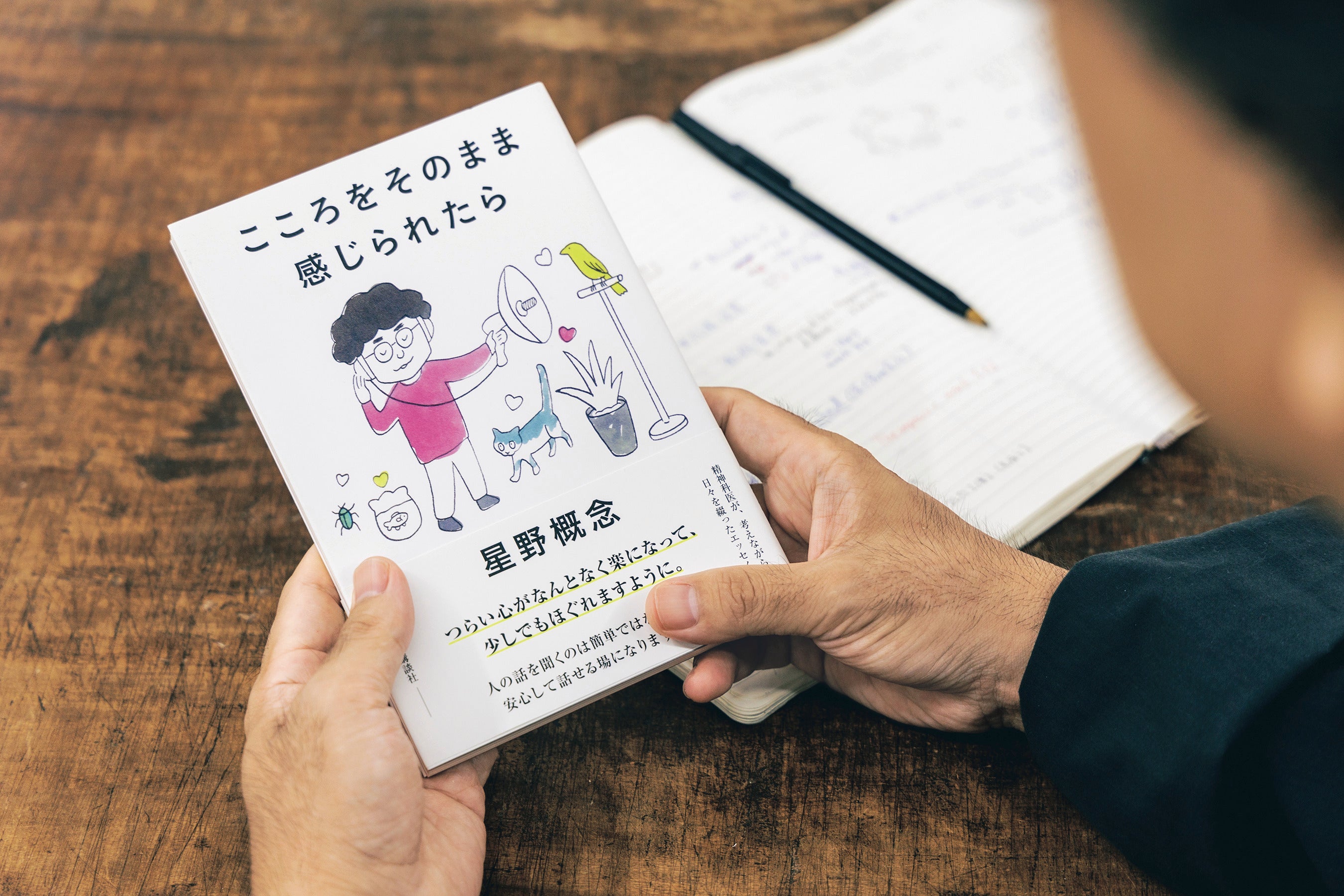
「メンタルヘルスに携わるようになって、しばらくは診断学のガイドラインに沿った治療をしていました。でも "この症状ならこの薬"というような教えられた診断で手を尽くしても、多くの人があまり良くならないんですよね。どうしたらいいかを考えていた時、愛読していた精神科医の神田橋條治さんの本の内容が響き始めました。その人がどうしたら少しでもラクになるかを考えるには、その人が置かれている周りの環境や、その人自身に思いを馳せながら話を聞いて考えるのが必要だと気づいたんです。今思えば当然ですが、教育って怖くて、目の前にいる人を置いてけぼりにして、正しく教えられた道筋に沿おうとしてしまう。その体験は、僕にとって結構なパラダイムシフトになりました」

ゆかいワークショップ「声に触れる」企画内で開催されている「星野概念のメンタルヘルススーパー銭湯」での風景。
フィンランド発祥のオープンダイアローグという対話実践と、サウナを組み合わせて、こころを紐解くユニークな試み。
〈神田ポート〉で不定期開催。(写真:池田晶紀)
精神医学的に患者を見立てることが王道的な医者の本分だとすると、星野さんのやり方は、その人がどんな人で何に困っているのか、医学的な目線では見えない側面を見ようとすること。
「そのためには対話をする必要がある。何でどう困っているかを明らかにして、どうしたら少しでもラクにしていけるかを考える。時間はかかるけど、続けていると何かしらの変化が起こるんですよね。もうひとつ、僕は養生というのも重視していて。食事や運動や生活のリズム、それぞれに合った予防方法を一緒に探します。そうすると不調になりにくくなるんですよね」
診察室以外のスペースやオンライン上に対話の場を設けたり、対話とサウナを組み合わせたイベントを開催したり、メンタルヘルスを追求する試みは、様々なシーンへと広がりつつある。そしてそのヒントは、愛して止まない酒にもあった。
「最初はただ熱燗が好きで、自分の体に合う気がして飲んでいただけなんですけど、そのうち造られ方を深掘りするようになったら、さらに面白くなって。菌がバトンタッチしながら醸していく日本酒の発酵の過程も、本で初めて知ったんですけど、すごく素敵なことのように思えたんですよね。その頃に出会ったのが、現在、茨城の〈月の井酒造店〉の杜氏を務めている石川達也さんの酒でした」

日本酒や発酵はもとより、その興味は石川さんの酒造りの精神にもシフトしていった。
「石川さんのインタビュー記事などに、酒造りの主役は菌で、菌があるがままに活動できる環境づくりをするのが蔵人であり、杜氏なのだとあった。そのことが、僕が考えていたメンタルヘルスの感覚と勝手に重なったんですよね。僕は辛さを感じる人のお手伝いはできるけれど、良くなっていったり、何かを決めたり、最終的なブレイクスルーって本人にしかできない。でも、そのプロセスに居続けることはできるし、誰もいないよりも力になるんじゃないか。そういう自分のスタンスが、石川さんの酒造りの話のなかで語られているように思えたんです」
そして尊敬する石川さんへ猛アプローチするうち、幸運にもメールをし合ったり、蔵を見学させてもらったりする間柄になった。実際に、しんとした液体が発酵して沸き出すのを見守る姿に触れて、得たことは大きかったという。
「それは自分が真理だと思っていた、待つということをエンパワーメントしてくれた体験でした。石川さんから得た酒にまつわる体験や学びに、自分はとてもインスパイアされていて、それなしでは今の自分はなかったと感じています」

星野さんにとって忘れられない食というのも、蔵見学の後、石川さんを始め、日本酒を醸す蔵人たちと一緒に囲む夕食の時間にある。
「一日中、蔵で酒造りをじっくり見学させてもらってから、夜に時々ごはんをご一緒させていただくんです。彼らと普段の食卓をともにするのは、おそれ多くも嬉しくて。だって、僕にとって尊い仕事をしてくれている思い入れのある人たちなんですよ。彼らと食卓を囲んで、その時々で酒造りで疑問に思うことを聞いたり、ただ笑い合ったり、晩酌に混ぜてもらえることに、すごく感動するんですよね。それは僕にとって、何にも代えがたい貴重な体験なんです」
その食卓には必ず、〈月の井〉の酒がある。
「晩酌の時はいつも、頭と呼ばれる現場キャプテンが燗つけ係なんですけど、ふたを空けたポットに徳利を入れて、手で持てないくらい熱々の温度で飲ませてくれるんです。石川さんの酒って、すごくしっかりした造りなので、温度を上げても、その分、味にふくらみが出るんですよね。日々の気取らない飲み方を共有しながら飲むのも嬉しいし、その燗酒の旨さ、なんだこれは!という感覚は、その場の雰囲気も相まって、時が経ってなお忘れることができません」
わたしの素

昔から、豆やおかきがとにかく好きなんですよ。〈風雅〉の「風雅巻き」は最初、たまたまどこかで出してもらったのかな。おいしいと思って調べたら、中身の豆と味の組み合わせがいろいろあって、そんなの楽しいに決まってるし、海苔もパリパリでおいしいし。それに、手でひとつひとつ豆を巻いていると知って、すごい!と思って、取り
寄せて常備するようになりました。中身は豆と海苔なので、小腹が空いた夜にも2~3本食べて重くなく、ナッツだけを単体で食べるより味わい深い。ほかの何かでは替えがきかないんですね。好きなのは定番の醤油大豆ですが、醤油カシューナッツも旨い。後者は、ボリュームも特別感もあるので一日1本までと決めています。(本人購入品)
profile

星野 概念 / ほしの がいねん
精神科医など / 1978年生まれ。
病院勤務や訪問診療の傍ら、執筆や音楽活動も行う。対話と養生を軸に、漢方や発酵などにもヒントを得て、様々な心の不調と向き合っている。著書に『こころをそのまま感じられたら』『ないようである、かもしれない』、いとうせいこうとの共著『ラブという薬』など。
Credit : FRaU編集部
photo:Masanori Kaneshita
text & edit:Asuka Ochi
連載
オイシサノトビラの扉
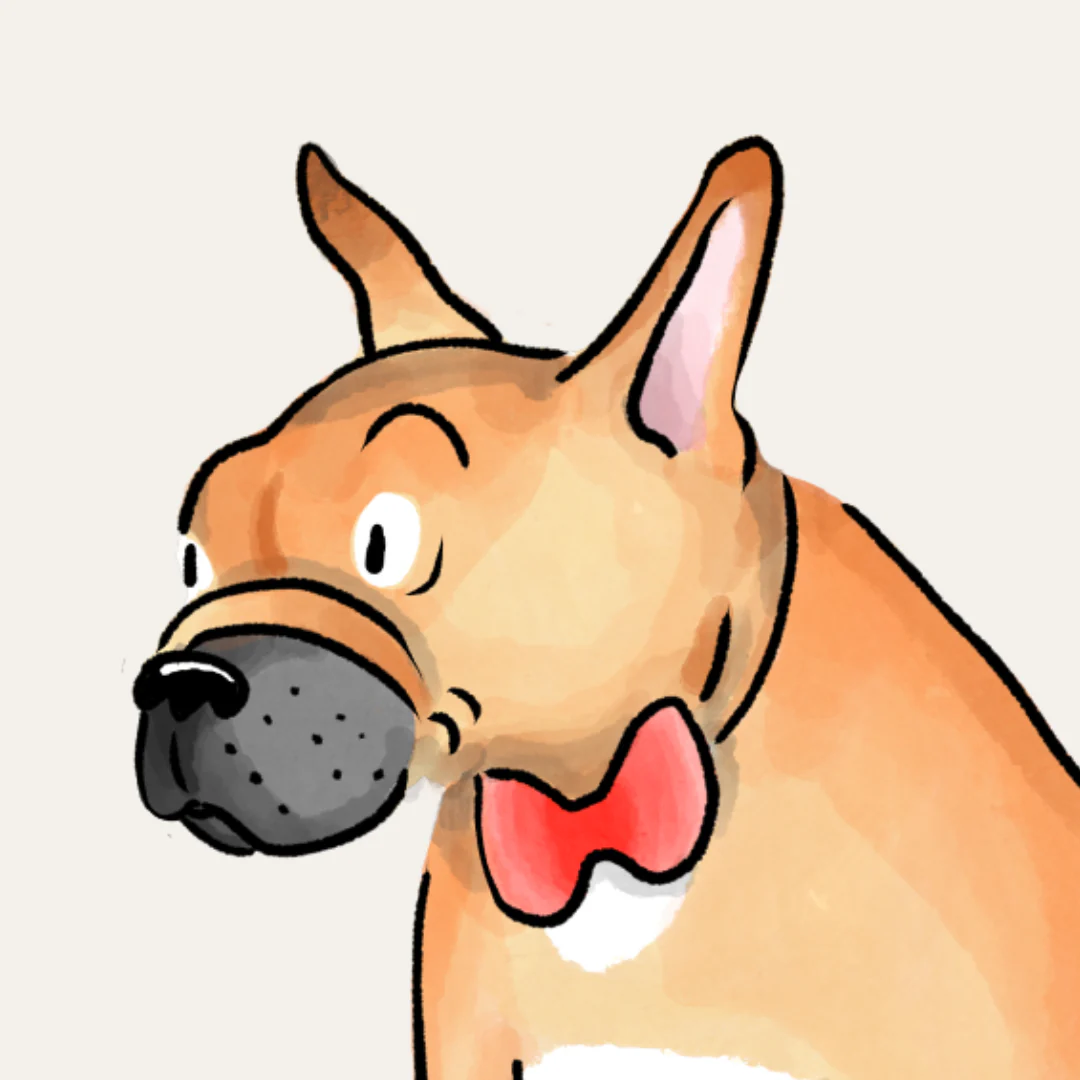
オイシサノトビラ
「おいしさって、なんだろう?」をテーマに、その人の生きる素となるような食事との出合いやきっかけをつくることを目指しています。